
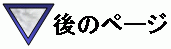
センター試験というのは計算用紙が配布されない、
おかしい試験です。
数学的センスのある人にはとても嫌われる形の試験と思います。
計算用紙が無いので、問題用紙のスペースを計算用紙として使って計算します。
その際に、大きな字で計算式を書き込むようにしてください。
以下のタイプのセンター試験の計算問題は、以下のように、なるべく広い空きスペースを使って計算するようにしましょう。
その際に分断された計算式は、線で結んで、スペースの島から遠くの島まで自由に計算式が行き来できるようにしましょう。
スペースが無くても、計算式の字は大きな字で書きましょう。
計算式の続きを別のページに飛んで行って行なわせるときは、ジャンプ点の番号①、②等の目印で別のページの計算式と結びつけましょう。
計算ミスを無くす方法
のサイトの助言が良いと思います。
このサイトでは、計算ミスを少なくするための1つとして、
とにかく計算方法をどんどん覚えること
を推薦してます。
的確なアドバイスと思います。
例えば、以下のような計算があります。
この式は1行目から4行目まで計算していくのですが、
この1行目から直ぐに4行目を書けるように、
計算方法をおぼえてしまえば、
計算ミスが確実に少なくなります。
下の式でも、1行目から直ぐに4行目を書けるように、
計算方法を覚えてください。
上のように覚えて短縮した計算方法は、以下の様な計算に適用できます。
リンク:
高校数学の目次
おかしい試験です。
数学的センスのある人にはとても嫌われる形の試験と思います。
計算用紙が無いので、問題用紙のスペースを計算用紙として使って計算します。
その際に、大きな字で計算式を書き込むようにしてください。
以下のタイプのセンター試験の計算問題は、以下のように、なるべく広い空きスペースを使って計算するようにしましょう。
その際に分断された計算式は、線で結んで、スペースの島から遠くの島まで自由に計算式が行き来できるようにしましょう。
スペースが無くても、計算式の字は大きな字で書きましょう。
計算式の続きを別のページに飛んで行って行なわせるときは、ジャンプ点の番号①、②等の目印で別のページの計算式と結びつけましょう。
計算ミスを無くす方法
のサイトの助言が良いと思います。
このサイトでは、計算ミスを少なくするための1つとして、
とにかく計算方法をどんどん覚えること
を推薦してます。
的確なアドバイスと思います。
例えば、以下のような計算があります。
この1行目から直ぐに4行目を書けるように、
計算方法をおぼえてしまえば、
計算ミスが確実に少なくなります。
下の式でも、1行目から直ぐに4行目を書けるように、
計算方法を覚えてください。
上のように覚えて短縮した計算方法は、以下の様な計算に適用できます。
リンク:
高校数学の目次





























































