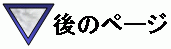大人のための数学勉強法
「どんな問題も解ける10のアプローチ」問題集の使い方
●「わかる」と「できる」は違う
●問題集の「解答」について
●問題集に載っている問題は試験に出ない
●なぜできなかったのか?
●問題ができたときは
の内容が面白い。
そして、数学ができるようになる大切なポイントを教えられました。
①問題が解けない。
②解き方を見る。
③再度問題を解く。
④問題が良く解けた。
この①から④を繰り返して数学を学んでいるつもり、
という数学の勉強方法は、全然数学の勉強になっていない。
たしかに、数学の解き方を1つ1つ覚えても、ある程度問題が解けるようになる。
しかし、それでは、本当の数学を学んだことにはならない。
その問題の解き方を覚えるのは数学を学ぶ優先順位の第2番目です。
数学では『解答を読んで理解すること』と『何も見ずに自力で論理を組み立てて解答を作成できること』には大き なギャップがあります。
解答を読んで納得しても,いざ解答を作成する立場になって初めて「なぜこう考えるのか?」という疑問を抱いたり,意味を勘違いしている概念や公式があったりと,自分が復習すべき箇所に気付くことも少なくありません。
数学を学ぶ第1の優先順位は、その問題に初めて直面したとき、なぜ解けなかったのかの原因を分析して、
その問題の解き方を自力で導き出す根源的方法を探ることにあります。
その根源的方法を知っていれば、その問題に初めて出会ったときにもその問題が解けただろう、そういう方法を見つけ出す。数学の技(わざ)を磨くことです。
そして、その技で解けるかもしれない(解き方自体も)新しい問題を探して、その問題が解けるようになっていることを調べます。
その、根源的方法を使って、解き方が新しい問題が解けてはじめて、最初に解けなかった問題が解けるようになったと考えるのです。
解き方を教わって解けるようになった問題は、解けるようになったものとは見なさないのです。
そういう技を磨くには、1つ1つの未知の問題が貴重で、なるべく解答を見ないで解きます。
解答を見てしまったら、その問題を解く数学の技を磨く材料にはならなくなってしまうからです。
だから、そういう数学の勉強をしている人に、問題の解き方を見せてしまうというのは、とても悪い事をしているとも考えられます。
このブログでは、
今までは、問題と、その解答とを併記して説明していましたが、
それは、数学の考える力、問題を解く力を養うのには悪い作用しか与えて来なかったのではないかと反省しています。
これからは、このブログは、過去の記事にまでさかのぼって、
問題と、その解き方とは、分けて書いて、
読者が、先ずその問題を自力で解くことができるようにし、数学の技を磨くチャンスを読者から奪わないようにします。
それと、その問題の解き方の説明においても、単に問題の解き方を提示するのでは無く、
その解き方が、どのような方法を用いることで導き出せるかを説明するようにしたいと思います。
(数学の問題を解く根源的方法)
数学の問題が解ける根源的方法は、簡単に導き出せる公式をことごとく発見して、その公式を速やかに導き出せるようにしておくことです。
その公式を導き出すほんの少しのヒントを覚えて、そのヒントに従ってその公式を直ちに導き出せるように訓練しておくことです。
そうすれば、少しのヒントを覚えるだけで、とても多くの公式を覚えているのと同じ効果が得られます。とても多くの公式を覚えているのと同じなので、多くの問題が楽に解けます。
(問題の解説を見る前に、問題を簡単にして解くこと)
数学の問題が解ける根源的方法はどうやって発見できるのでしょうか。
それには、自力で解けない問題があった場合に、その問題を極力簡単な問題に変えてみて、その簡単な問題が解けるかを考えます。その簡単な問題が解けなかったら、元の問題の解法を見ても良いです。その解法を、その簡単な問題を解くヒントにします。
そのヒントも、問題が解ける根源的方法に近い知識になります。
(数学の公式の覚え方)
数学の公式は覚えられません(覚えていてもすぐに忘れる)。特に、覚えていた公式に似ている公式を覚えようとする場合に、その新しい公式に似ている、旧くから覚えていた公式は、新しい公式を覚える必要のために忘れ去られます。
そういうふうに、数学の公式は覚えられないものです。
そのため、忘れかけている不確かな公式を思い出して使うのでは無く、毎回公式を導き出して使うと良いです。公式を出来るだけ速やかに導き出せるように、公式を導き出す道を洗練させておくのが、ある意味、「公式を覚える」作業です。
新しい問題が解けなかったら、その問題を解くために役立つ公式で、未だ知らなかった、速やかに導き出せる、隠れた公式を探します。
あるいは、毎回導出する公式の導出に時間がかかる場合は、その公式を導出し易くする、速やかに導き出すために役立つ公式を探すのです。
その新しい公式が見つかったら、その新しい公式を導き出すほんの少しのヒントを覚えて、そのヒントに従ってその公式を直ちに導き出して使えるように練習します。
これが、数学の問題が解けるようになる根源的な方法だと思います。
すなわち、新しい問題が解けなかったら、あるいは、毎回導出している公式の導出に時間がかかっている場合は、
その問題だけが解けるその問題の解き方だけの解答を覚えるのでは無く、
①できるだけ多くの問題を解くために使えて、その問題を解くためにも使える公式で、
②少しのヒントで速やかに導き出せる公式を発見する。
③そして、その公式を速やかに導き出して問題を解くのに使えるように練習するのです。
その練習をするのは、計算ミスを減らす練習をすることでもあります。
(補足)
自力で数学の問題を解くときには、解こうとして、問題を解き得るあらゆる可能性を考えて、解く道を自分で探ります。どういうときにどの方向に進むと、自分が解ける問題になるか、という、解き方の可能性のネットワークを見通す力がついてきます。そのネットワークの認識が正しいか否かは、問題が解けるという実績によって確かめられていきます。
そういう、実際の解答を作るときに考えた、「解き方の可能性のネットワーク」には、問題集の解答の解説にかかれている情報の数倍の情報量があります。
そのように、自力で問題を解くときには、実際の解答の手順の情報の数倍の「思索された解き方の可能性」の情報が得られます。
その自分が思索して生み出した「解き方の可能性の情報」は、次の問題を解くときにも思い出されて来て、増々、解き方のネットワークが広がっていきます。
その情報量の違いが「数学の力」であり、大学入試で初見の問題を解くのに必要な力です。
(勉強の例1)
例えば、数学の教科書の「例題」を、その解説を読まずに自力で「例題」を解く。 「例題」は解説を読まずに自力で解こうとすると、とても難しい問題になります。1日がかりで1つの「例題」を自力で解くと良い。1日かけても解けなかったら例題の解説を見ても良いです。
授業でその例題が説明される前に、そのようにして1日がかりで自力で例題を解いておきます。
そうすれば、かなり数学の力がつくと思います。
1日かけて「例題」を解こうとして思索する間に、かなりな量の「思索された解き方の可能性」の情報が考え出されます。
例題が解けなくても、その考えだされる多量の情報を得るために、1日かけてもがんばるのです。
かなりな量の「思索された解き方の可能性」の情報を考え出し続けることができる魅力のある問題を自力で解き続けると良いと思います。
数学の教科書の「例題」というのは、解説が短いので、なぜ自力で解けなかったのかと思ってしまう、(難しい問題なのですが)解けないハズが無い、と思うくやしさがある。そのため、1日中、解こうと考え続けることができる「魅力」のある問題です。
そういう、飽きずに考え続けることができる、魅力のある問題を自力で解くのが良いと思います。
(勉強の例2)
獲得した数学の「思索された解き方の可能性」の情報を忘れてしまわないように、毎日、1問は、数学の問題を解き続けることも大事な習慣です。
《まっつんのお役立ちチャンネル》
「勉強全般 1習得ステップ&本返し縫い勉強の大切さ」
https://youtu.be/svd01YQOhBs
また、毎日解く1問の何かの数学の問題を解いているときに、思い出されて来る情報こそが数学の「根源的な解き方の情報」です。問題集の問題の解説に書かれている情報は、数学の他の問題を解こうとしているときに思い出されて来ることが少なければ、「それは根源的な解き方の情報」では無かったことが分かります。
リンク:
高校数学の目次
計算ミス対策:計算ミスの改善方法