
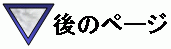
「微分・積分」の勉強
(5)微分の知識:
以下の合成関数の微分の公式があります。
以下の様に微分の計算を楽にするときに使う公式です。
(この公式には一定の縛り(成立条件)があります。それは、「f(g)の微分が存在し、g(x)の微分が存在する(微分可能)必要がある」という前提条件です。)
関数の微分が存在しない典型的な例として、以下の図の関数yはx=0でxによる微分が存在しません。
合成関数の微分の公式である以下の式:
は、関数f(g)とg(x)があり、その関数の合成関数の、
y=f(g(x))=h(x)
という関数を作った場合に、
変数xのある値xに対応する変数g=g(x)があり、
変数のその値において、
(dg/dx)=g’(x)の有限の値の微分係数が存在し(微分可能)、
変数gのその値において、
(dh/dg)=f’(g)の有限の微分係数が存在する(微分可能)
の場合に、
変数xとgがそれらの値の場合において、
f’(g)=(df/dg)と、
g’(x)=(dg/dx)との積が、
h’(x)=(dh/ dx)になる、
という公式です。
どの関数f(g)とg(x)で作った合成関数についても、この条件が満足されれば、この公式が成り立つ、という公式です。
「関数が微分可能(有限の値の確定した値の微分係数が存在する)」
という意味は、
「関数が、その変数のその値に限って、その変数で微分可能であれば良く、その変数のその他の値での関数の微分可能性は関係しない」
という意味です。
実はこの合成関数の微分の公式は以下の同様な式で表された公式群の一部です。
この各公式には、先ず、以下の縛り(成立条件)があります。
その縛りというのは、
「上の式の様に微小量の割り算であらわした式の、ΔhもΔgもΔxも、何れも微小量でなけばならない」
とういう条件です。
例えば、関数g(x)=(1/x)を使った場合、
Δg=Δ(1/x)が、
x→0で、微小量にならないから、
x→0の場合には、関数g(x)=(1/x)を使うことができません。
また、更にその上に、各関数の微分可能条件も(あたりまえの条件のように見えますが)あえて意識する必要があります。
その理由は、xの位置に応じて、Δgが正から0になって負に変わる場合も考えられるからです。
「関数が微分可能(有限の値の確定した値の微分係数が存在する)」
という意味は、
「関数が、その変数のその値に限って、その変数で微分可能であれば良く、その変数のその他の値での関数の微分可能性は関係しない」
という意味です。
(注意)
以下の式で:
Δgが微小量より更に小さい真正の0になる場合を考えずに合成関数の微分の公式を証明したつもりの偽証明が流通しています。自分の「分からないものは分からない」センスを大切にして、偽物に騙され無いように、注意しましょう。
Δgが微小量より更に小さい真正の0になる場合は、以下で詳しく調べます。それ以外の場合は微小量の割り算で公式が説明できるので、高校2年生でも、以下の説明を読んで、その後は公式を覚えてしまいましょう。
Δgが微小量より更に小さい真正の0になる場合を、以下の合成関数の例で考えます。
【事例1】
次に、以下の微分を考えます。
この式5を見ると、
x→0
の場合に、関数gの微分が:
となり、微分が0になることがわかります。
その場合は、
Δg=0(微小量より更に小さい真正の0)になります。
(dh/dg)が微分可能(値が確定した有限値になる)なら、
となるので、
Δxに対してΔgが真正の0になるのと同時にΔhも真正の0になります。
そのため、
x→0の場合に、
になります。実際に式3をxで微分すれば、その通りになっていることがわかります。
この関数hの微分を、Δgを含めて展開すると:
となります。
このように、ほとんどΔg=0である(真正の0である)とも言える関数g(x)の場合にも、
Δgが真正の0で無いただの微小量の場合と同じ形の公式:
が成り立っていました。
この事例は、0では無い小さなΔxが存在すれば、 ΔgがΔxの2乗程度の極めて小さい値になりますが、Δgは厳密には0にはならないので助かりました。
しかし、以下の図のような、有限な範囲でg(x)の値が一定値で続く関数g(x)の場合は、0では無い小さなΔxに対して厳密にΔg=0になります。(この関数gは-1<x<1の範囲でg(x)=0であり、かつ、(dg/dx)=0です)。そういう関数g(x)の場合には、この事例の計算方法では、正しい答えが得られません。
その場合にも有効な結果を得る計算方法が以下の様に考えられます。
着目点は、hが微分可能であれば、(Δh/Δg)の値は、Δgがどれだけ小さくても値が安定して(dh/dg)に収束することです。
計算の初めの時点から、(Δh/Δg)の式のかわりに、有限値の微分の値(dh/dg)を使って計算するならば、上の計算は、
有限値(dh/dg)・(値が0に収束する(Δg/Δx))
の計算に置き換えることができます。
そうすれば、小さなΔxでΔgが厳密に0(真正の0)になっても、
式の中でΔgが分母に来ることが無いので、
Δgがどうであれ合成関数の微分の公式が成り立ちます。
hのgによる微分が有限の値の(dh/dg)に収束する(微分可能)ならば、合成関数の微分の公式を成り立たせる結果を導き出せます。
【合成関数の微分の公式の証明】
上の事例でΔgが真正の0になる場合を考えましたが、Δgが真正の0になるという発想は、Δxが0で無い場合にΔgが真正の0になる場合があるという、g(x)の関数の性質に由来する問題です。
以下では、hをgの関数と考え、gをxの関数と考え、g(x)の関数の性質に左右されない証明をします。
(証明開始)
(1)先ず、hをgの関数と考え、hはgが変化したときにどのくらい変化するか調べるため、hをgで微分する。
hがgで微分可能((Δh/Δg)の極限が有限の値になる)なら、
Δhが以下の式であらわされる。
(2)その場合に、以下の式が成り立つ。
(証明おわり)
こう考えれば合成関数の微分の公式が自然に証明できます。
この証明の中には、Δx≠0のときにΔgが0(真正の0)になる場合も含まれています。
(1)で考えた(Δh/Δg)は、gが変化する場合のhの変化の割合を調べたものであり、gが変化しないならhも変化しないと考えています。
そして、(2)では、Δgが0になる場合も考慮されています。
すなわち、
(2)では、
Δg=0なら、
Δh=0になり、
(Δh/Δx)=0
になります。
また、変数xのある値で、(Δh/Δx)≠0となる場合に(Δg/Δx)=0となる不適切な関数g(x)を選んだ場合は、
変数xのその値でΔgが真正の0になります。それとともに、変数xのその値に対応するg(x)の値では、関数hのgによる微分(Δh/Δg)が無限大になろうとし、関数hがその値のgでは微分可能では無くなります。
そのため、そのようにdg/dx=0とする変数xの値(そのxに対応するg(x)の値)においては、公式が適用できなくなります。
「関数が微分可能」という条件は、このように、不適切な関数g(x)が使われる場合でも、変数xの定義域の範囲、および関数hを微分する変数としてのgの値の定義域の範囲を、公式が適用できる範囲に制限することで公式を守っています。
なお、以上の証明の基礎となった以下の置き換えの公式(微分された関数が微分可能であることを前提にする)があります。これは、その他の全ての公式の証明に使えます。
【事例2】
次に、各関数が微分可能では無い場合にどうなるかを事例2で調べます。
以下の合成関数を考えます。
ここで、式2から、
x→0
の場合に、
g→0となります。
次に、以下の微分を考えます。
この式5を見ると、
x→0
の場合に、関数gの微分が0になることがわかります。
すなわち、
Δg=0(微小量より更に小さい真正の0)です。
一方、式4を見ると、
g→0 (x→0)
の場合に、
(dh/dg)=±∞ になり、
関数hが(gの値が0の場合は)変数としてのgで微分可能(確定した有限値の微分係数を持つ)では無いことがわかります。また、関数hは、gの値が0以外の値の場合は、変数としてのgで微分可能であることがわかります。
そのため、
g→0 (x→0)
の場合に、
合成関数の微分の公式が成り立ちません。
公式が適用できないことは以下のように確かめられます。
式3を直接にxで微分すれば、
になります。
その結果と、
x→0 の場合に、式5から得た
とを合わせた公式の式:
は計算できません。
一方、xの値が0以外の値(同時にgの値が0以外の値)の場合は問題が無く、合成関数の微分の公式が適用できます。
(この事例からも、各関数の微分可能性が、合成関数の微分の公式に必須な条件だと分かります)
合成関数の微分の公式は微分の連鎖律とも呼ばれています。
「f(g)の微分が存在し、g(x)の微分が存在する必要がある」という前提条件の意味を、更に以下の事例3でも考えます。
【事例3】
以下の合成関数を考えます。
次に、以下の微分を考えます。
この式5を見ると、
x→0
の場合に、関数gの微分(確定した有限値の微分係数)が存在しないことがわかります。
そもそも、微分をする以前に、
x→0
の場合に、関数gはプラスマイナス無限大になるので、
x=0は関数gの定義域から外れます。
そのためx=0では(定義域の外ですので)関数gは使えません。
また、式4を見ると、
g→0 (x→±∞)
の場合に、関数 f の微分が存在しないことがわかります。
そのため、以下の計算は、
x ≠ 0 (g ≠ ±∞) and x ≠ ±∞ (g ≠ 0)
の場合にのみ適用できます。
x=0の場合の関数 f の微分については、
式3を直接xで微分して確かめる必要があります。
以上の調査の結果を見ると、
合成関数の微分の公式の縛り(成立条件)である
「f(g)の微分が存在し(確定した有限値になる)、
g(x)の微分が存在する(確定した有限値になる)」
という前提条件は、
「式を0で割り算する計算をしてはいけない」
という計算の縛りと同じ様な意味を持っていることがわかります。
すなわち、「微分可能」という前提条件は、
「0で割り算しない場合に限る」という前提条件 、
言いかえると、
「計算の違反が無い計算に限る」という前提条件、
を加えて微分の式を書くことだと考えます。
そういう「万能の条件」を正しく組み込んで計算するならば、どの様な計算もできてしまいます。
(その条件を正しく組み込まないでその計算をまねした計算は計算違反がある誤った計算になります)
その通りに、どの様な計算もできるのが、合成関数の微分の公式やその他の公式が成り立つ根拠だと考えます。
リンク:
高校数学の目次
(5)微分の知識:
以下の合成関数の微分の公式があります。
以下の様に微分の計算を楽にするときに使う公式です。
(この公式には一定の縛り(成立条件)があります。それは、「f(g)の微分が存在し、g(x)の微分が存在する(微分可能)必要がある」という前提条件です。)
関数の微分が存在しない典型的な例として、以下の図の関数yはx=0でxによる微分が存在しません。
合成関数の微分の公式である以下の式:
は、関数f(g)とg(x)があり、その関数の合成関数の、
y=f(g(x))=h(x)
という関数を作った場合に、
変数xのある値xに対応する変数g=g(x)があり、
変数のその値において、
(dg/dx)=g’(x)の有限の値の微分係数が存在し(微分可能)、
変数gのその値において、
(dh/dg)=f’(g)の有限の微分係数が存在する(微分可能)
の場合に、
変数xとgがそれらの値の場合において、
f’(g)=(df/dg)と、
g’(x)=(dg/dx)との積が、
h’(x)=(dh/ dx)になる、
という公式です。
どの関数f(g)とg(x)で作った合成関数についても、この条件が満足されれば、この公式が成り立つ、という公式です。
「関数が微分可能(有限の値の確定した値の微分係数が存在する)」
という意味は、
「関数が、その変数のその値に限って、その変数で微分可能であれば良く、その変数のその他の値での関数の微分可能性は関係しない」
という意味です。
実はこの合成関数の微分の公式は以下の同様な式で表された公式群の一部です。
この各公式には、先ず、以下の縛り(成立条件)があります。
その縛りというのは、
「上の式の様に微小量の割り算であらわした式の、ΔhもΔgもΔxも、何れも微小量でなけばならない」
とういう条件です。
例えば、関数g(x)=(1/x)を使った場合、
Δg=Δ(1/x)が、
x→0で、微小量にならないから、
x→0の場合には、関数g(x)=(1/x)を使うことができません。
また、更にその上に、各関数の微分可能条件も(あたりまえの条件のように見えますが)あえて意識する必要があります。
その理由は、xの位置に応じて、Δgが正から0になって負に変わる場合も考えられるからです。
「関数が微分可能(有限の値の確定した値の微分係数が存在する)」
という意味は、
「関数が、その変数のその値に限って、その変数で微分可能であれば良く、その変数のその他の値での関数の微分可能性は関係しない」
という意味です。
(注意)
以下の式で:
Δgが微小量より更に小さい真正の0になる場合を考えずに合成関数の微分の公式を証明したつもりの偽証明が流通しています。自分の「分からないものは分からない」センスを大切にして、偽物に騙され無いように、注意しましょう。
Δgが微小量より更に小さい真正の0になる場合は、以下で詳しく調べます。それ以外の場合は微小量の割り算で公式が説明できるので、高校2年生でも、以下の説明を読んで、その後は公式を覚えてしまいましょう。
Δgが微小量より更に小さい真正の0になる場合を、以下の合成関数の例で考えます。
【事例1】
次に、以下の微分を考えます。
この式5を見ると、
x→0
の場合に、関数gの微分が:
となり、微分が0になることがわかります。
その場合は、
Δg=0(微小量より更に小さい真正の0)になります。
(dh/dg)が微分可能(値が確定した有限値になる)なら、
となるので、
Δxに対してΔgが真正の0になるのと同時にΔhも真正の0になります。
そのため、
x→0の場合に、
になります。実際に式3をxで微分すれば、その通りになっていることがわかります。
この関数hの微分を、Δgを含めて展開すると:
となります。
このように、ほとんどΔg=0である(真正の0である)とも言える関数g(x)の場合にも、
Δgが真正の0で無いただの微小量の場合と同じ形の公式:
が成り立っていました。
この事例は、0では無い小さなΔxが存在すれば、 ΔgがΔxの2乗程度の極めて小さい値になりますが、Δgは厳密には0にはならないので助かりました。
しかし、以下の図のような、有限な範囲でg(x)の値が一定値で続く関数g(x)の場合は、0では無い小さなΔxに対して厳密にΔg=0になります。(この関数gは-1<x<1の範囲でg(x)=0であり、かつ、(dg/dx)=0です)。そういう関数g(x)の場合には、この事例の計算方法では、正しい答えが得られません。
着目点は、hが微分可能であれば、(Δh/Δg)の値は、Δgがどれだけ小さくても値が安定して(dh/dg)に収束することです。
計算の初めの時点から、(Δh/Δg)の式のかわりに、有限値の微分の値(dh/dg)を使って計算するならば、上の計算は、
有限値(dh/dg)・(値が0に収束する(Δg/Δx))
の計算に置き換えることができます。
そうすれば、小さなΔxでΔgが厳密に0(真正の0)になっても、
式の中でΔgが分母に来ることが無いので、
Δgがどうであれ合成関数の微分の公式が成り立ちます。
hのgによる微分が有限の値の(dh/dg)に収束する(微分可能)ならば、合成関数の微分の公式を成り立たせる結果を導き出せます。
【合成関数の微分の公式の証明】
上の事例でΔgが真正の0になる場合を考えましたが、Δgが真正の0になるという発想は、Δxが0で無い場合にΔgが真正の0になる場合があるという、g(x)の関数の性質に由来する問題です。
以下では、hをgの関数と考え、gをxの関数と考え、g(x)の関数の性質に左右されない証明をします。
(証明開始)
(1)先ず、hをgの関数と考え、hはgが変化したときにどのくらい変化するか調べるため、hをgで微分する。
hがgで微分可能((Δh/Δg)の極限が有限の値になる)なら、
Δhが以下の式であらわされる。
(2)その場合に、以下の式が成り立つ。
(証明おわり)
こう考えれば合成関数の微分の公式が自然に証明できます。
この証明の中には、Δx≠0のときにΔgが0(真正の0)になる場合も含まれています。
(1)で考えた(Δh/Δg)は、gが変化する場合のhの変化の割合を調べたものであり、gが変化しないならhも変化しないと考えています。
そして、(2)では、Δgが0になる場合も考慮されています。
すなわち、
(2)では、
Δg=0なら、
Δh=0になり、
(Δh/Δx)=0
になります。
また、変数xのある値で、(Δh/Δx)≠0となる場合に(Δg/Δx)=0となる不適切な関数g(x)を選んだ場合は、
変数xのその値でΔgが真正の0になります。それとともに、変数xのその値に対応するg(x)の値では、関数hのgによる微分(Δh/Δg)が無限大になろうとし、関数hがその値のgでは微分可能では無くなります。
そのため、そのようにdg/dx=0とする変数xの値(そのxに対応するg(x)の値)においては、公式が適用できなくなります。
「関数が微分可能」という条件は、このように、不適切な関数g(x)が使われる場合でも、変数xの定義域の範囲、および関数hを微分する変数としてのgの値の定義域の範囲を、公式が適用できる範囲に制限することで公式を守っています。
なお、以上の証明の基礎となった以下の置き換えの公式(微分された関数が微分可能であることを前提にする)があります。これは、その他の全ての公式の証明に使えます。
【事例2】
次に、各関数が微分可能では無い場合にどうなるかを事例2で調べます。
以下の合成関数を考えます。
ここで、式2から、
x→0
の場合に、
g→0となります。
次に、以下の微分を考えます。
この式5を見ると、
x→0
の場合に、関数gの微分が0になることがわかります。
すなわち、
Δg=0(微小量より更に小さい真正の0)です。
一方、式4を見ると、
g→0 (x→0)
の場合に、
(dh/dg)=±∞ になり、
関数hが(gの値が0の場合は)変数としてのgで微分可能(確定した有限値の微分係数を持つ)では無いことがわかります。また、関数hは、gの値が0以外の値の場合は、変数としてのgで微分可能であることがわかります。
そのため、
g→0 (x→0)
の場合に、
合成関数の微分の公式が成り立ちません。
公式が適用できないことは以下のように確かめられます。
式3を直接にxで微分すれば、
になります。
その結果と、
x→0 の場合に、式5から得た
とを合わせた公式の式:
は計算できません。
一方、xの値が0以外の値(同時にgの値が0以外の値)の場合は問題が無く、合成関数の微分の公式が適用できます。
(この事例からも、各関数の微分可能性が、合成関数の微分の公式に必須な条件だと分かります)
合成関数の微分の公式は微分の連鎖律とも呼ばれています。
「f(g)の微分が存在し、g(x)の微分が存在する必要がある」という前提条件の意味を、更に以下の事例3でも考えます。
【事例3】
以下の合成関数を考えます。
次に、以下の微分を考えます。
この式5を見ると、
x→0
の場合に、関数gの微分(確定した有限値の微分係数)が存在しないことがわかります。
そもそも、微分をする以前に、
x→0
の場合に、関数gはプラスマイナス無限大になるので、
x=0は関数gの定義域から外れます。
そのためx=0では(定義域の外ですので)関数gは使えません。
また、式4を見ると、
g→0 (x→±∞)
の場合に、関数 f の微分が存在しないことがわかります。
そのため、以下の計算は、
x ≠ 0 (g ≠ ±∞) and x ≠ ±∞ (g ≠ 0)
の場合にのみ適用できます。
x=0の場合の関数 f の微分については、
式3を直接xで微分して確かめる必要があります。
以上の調査の結果を見ると、
合成関数の微分の公式の縛り(成立条件)である
「f(g)の微分が存在し(確定した有限値になる)、
g(x)の微分が存在する(確定した有限値になる)」
という前提条件は、
「式を0で割り算する計算をしてはいけない」
という計算の縛りと同じ様な意味を持っていることがわかります。
すなわち、「微分可能」という前提条件は、
「0で割り算しない場合に限る」という前提条件 、
言いかえると、
「計算の違反が無い計算に限る」という前提条件、
を加えて微分の式を書くことだと考えます。
そういう「万能の条件」を正しく組み込んで計算するならば、どの様な計算もできてしまいます。
(その条件を正しく組み込まないでその計算をまねした計算は計算違反がある誤った計算になります)
その通りに、どの様な計算もできるのが、合成関数の微分の公式やその他の公式が成り立つ根拠だと考えます。
リンク:
高校数学の目次

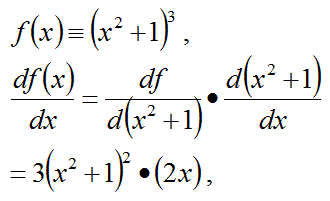























0 件のコメント:
コメントを投稿