
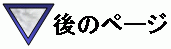
(ページ内リンク先)
▽はじめに
▽ 微分とは何か
▽定義の言い換え
▽関数の増減表
▽微分可能の定義の拡張=区間の端での微分可能の定義
▽接線の定義
▽右側微分係数と左側微分係数
▽関数の連続を前提にした、とある定理
▽微分不可能が微分可能に変わる例
▽行なって良い変数変換の条件
▽例題2.4
▽微分の式の前提条件:関数が存在すること
▽リーマン積分可能の定義
▽積分が不可能な関数
(はじめに)「微分・積分」の勉強について
高校2年生から、極限・微分・積分の「意味がわからない」「つまらない」「教わる計算方法が正しいと言える理由(証明)がわからない」で数学の学習から脱落する高校2年生が多いらしい。
その脱落の原因は、高校2年の極限・微分・積分の授業では、数学のうたい文句から外れた教育がされるからではないかと考えます。
すなわち、今までは、
「数学は、公式を正しく証明した後にその公式を使う」
と言って来たが、
高校2年生の、極限・微分・積分の授業からは、
「数学は、計算結果さえ合えば良い、途中の経緯は問わない、公式の証明は間違っていても問題視しない」
という教育思想が入り込み、
その思想の行き過ぎを避けるため、
「便利すぎる公式は、それをつかって直ぐ答えが得られてしまうから教えない」
という思想が混ざり、
数学教育に大きな濁りが入り込むので「微分積分がつまらない」となる原因があるのではないかと考えます。
その濁りに押し流され無いため、高校2年生も 公式を厳密に証明して納得してから使う、数学の心に従って極限・微分・積分の学習をして欲しいと考えます。
また、微分積分の正しい情報を与えてくれる、高校2年生が勉強しても、内容がわかり易くて良い微分積分の参考書の「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円 等の正しい情報を与えてくれる参考書を入手して、正しい情報を学習するのが良いと思います。
(微分とは何か)
先ず、微分とは何かを、微分可能のハッキリした定義を知ることで頭を整理しましょう。
微分可能の定義は:
(1)第1の定義の微分可能:
開放された開区間(a<x<b)の関数f(x)でxの右側微分係数と左側微分係数が一致する場合に微分係数が存在し微分可能であるとする定義。
(2)第2の定義の微分可能:
閉区間( a≦x≦b)の関数f(x)の、x=aとx=bとの区間の端点では、片側微分係数があるだけで、微分係数が存在し微分可能であるとする定義。
との2通りの定義があるので要注意です。
(微分積分学の基本定理との関係)
微分積分学の基本定理の根底を支えているのが微分可能の定義です。高校数学に与えられている微分可能の定義は第1の定義だけです。それにより、変数xの閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)であっても、微分可能な変数xの値の範囲は開区間(a<x<b)になってしまいます。そのため、高校数学では、開区間(a<x<b)で定義された関数 f(x)にしか、微分積分学の基本定理が成り立ちません。
一方、大学数学では、変数xが閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)の区間の端点x=a,bでも微分可能が定義されています。そのため、大学数学では、閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)にも微分積分学の基本定理が成り立つと教えられています。
ーー【区間の定義】ーー
「区間」という数学用語は、変数xの数直線上の1つの範囲内の、実数のすき間がない1かたまりの数の集合をあらわす数学用語である。
《神奈川大学》【定義 14.2.4.】
a, b を実数とする. a 以上かつ b 以下の実数をすべて集めた集合を [a, b] と書き, これを閉区 間と呼ぶ.
a より大きくかつ b 未満の実数をすべて集めた集合を (a, b) と書き, これを開区間と呼ぶ.
----定義おわり----
a≦x≦bを満足するxの区間という表現は、a≦x≦bの範囲内の全ての実数xという意味です。
-∞<x<∞という区間もあります。
区間はxの値の範囲を限定するためのa≦x≦bという式とは意味が異なることに注意する必要があります。
(A)「0≦x≦2の区間の変数xで定義された関数f(x)がその区間の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数である」という文では、
f(x)は、0≦x≦2の区間で1つながりに連続した関数f(x)として定義されます。連続関数は、平均値の定理を満足する関数です。。
(B)高校数学での、誤った連続関数の定義
「変数xの0≦x≦2の範囲内の値で関数f(x)が定義されていて、その関数f(x)が定義域の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数である」という高校数学の連続関数の定義では、f(x)は、例えば、
0<x<1で f(x)=0, この定義域内の各点で連続。
1<x<2で f(x)=1, この定義域内の各点で連続。
結局、0≦x≦2の範囲内の全ての定義域の各点で連続という関数も連続関数f(x)にされます。しかし、そのように、すき間をはさんだ2つの区間を合わせた複合区間を定義域とする関数は平均値の定理を満足しない。それは連続関数ではなく、その定義は正しい連続関数の定義ではない。
この例の様に、「区間」という用語は変数xの数直線上の、すき間がない1かたまりの実数の集合をあらわす。変数xの数直線上の「区間」では、その変数xの範囲内に実数のすき間があってはいけない。
区間a≦x≦bが命題の中に記載されている場合は、その範囲内の全ての実数xについて命題を検討する必要があります。被積分関数f(x)が定義されていない変数xの点があっても、その点も、その命題が検討されるべき点の1つです。
「区間」という用語は、特に重要な関数である連続関数の連続性を定義するために必要な、連続関数f(x)の変数xの集合体がいつも持っていなければならない連続性という重要な性質が「区間」という概念を用いてあらわされている。
すなわち、変数xの「区間」の性質で大切なのは、
「区間」のなかに変数xの値が隙間なく存在すること。
つまり所定範囲内での隙間が無い1かたまりの実数の集合という概念が「区間」という用語で定義されている。
《命題を検討すべき優先順位》
(1)関数f(x)を収める区間:
a≦x≦b(あるいはa<x<b)内の全ての実数x。
(2)その区間内の座標xにおける点。
(3)その区間内で関数f(x)が定義されている(f(x)の値が存在する)変数xの範囲(xの定義域):
a<x<(b-(a+b)/2) という範囲を定義域とする事や、
その範囲内の有理数のxのみを定義域とする事。
です。
区間について考えるという事は、その区間内の全ての実数の座標xの点を考え、その座標xでf(x)が定義されていない場合でも、その座標xについて考えるという事を意味します。すなわち、関数の微分可能性は、変数xの数直線上の実数が隙間なくつまっている区間を基にして定義される概念であって、関数の定義域を基にして定義される概念ではない。
区間を使って考える場合は、例えば、ある区間内の全ての実数の点のうち、関数f(x)が定義されず関数f(x)が連続で無い(数直線上の)点xについては、「区間内のその点xでf(x)が定義されず関数f(x)がその点xで連続していない」というふうに考えます。xの区間とは、そのようにして、関数の定義域よりも優先して考えるxの数直線上の、実数が隙間なく充填されている範囲の事です。
----------区間の定義終わり-------------
--(連続関数の定義の誤りに注意)---
また、高校で教えている連続関数の定義が間違っていて、それも微分可能の意味を理解できなくする原因になっているので要注意です。
小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」で定義されている連続関数の定義のように、大学では、定義域として、実数を完全に含んで連結している1つながりの「区間」の全ての実数のxで定義されている関数f(x)に限って連続関数を定義しています。
「区間Iで定義された関数f(x)がその定義域の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数であるという」
という表現が正しい連続関数の定義です。
ここで、「区間」という言葉が使われた時点で、それは1つながりの連結区間であって、それは、連続で無い点で分断された領域のことでは無い事に十分に注意する必要があります。
ーー注意のおわり---
関数f(x)であらわされるグラフの傾きは、以下のようにあらわされます。
この傾きは以下に説明する微分によって求めます。
---(定義2.1 「微分積分学入門」(横田 壽)67ページ---
(第1の定義の微分可能)
関数f(x) が、変数xのx0 を含むある開区間(a<x<b)で定義されているとき,極限値
(有限の傾きA)
が存在するならば,
関数f(x) は, x = x0 で微分可能(differentiable) であるといいます.
また,この極限値A を点x0 における微分係数といい,
で表わします.
-----(定義おわり)---------------------------
-----(定義の言い換え)---------------
微分可能の定義を理解するために、以下の様に、自分の言葉で定義を言い換えするのが良いと考えます。
(1)
区間を使った定義なので、
x0に近い(例えばx0から微小な値 δ 以内の誤差の)全ての実数の値の変数x(ただしx0を除外する)を考える。
(注意1)
微分可能の定義には、x0 と、それ以外の値のxとを考えるという条件が必ず入るので(曲線の傾きを求めるには、必ず異なる2点を使う必要がある)、x0以外の全ての実数の点を強制的に調べることを定義に加えている極限の定義と相性が良いので、極限を使って微分可能を定義している。
また、点x=x0でのf(x)の微分可能の定義は、点x=x0だけで定義されるのでは無く、x0の点とその近傍の点との点の集合全体を使って、x0の点でのf(x)の微分可能を定義している。高校数学に与えられている微分可能の定義は第1の定義だけです。
微分可能の第1の定義では、x0の点の左右の近傍の点の集合が存在する必要があり、その点の集合の真ん中の点が微分可能なx0の点です。
関数f(x)を与える点の集合がa≦x≦bの閉区間で定義されている場合に、その区間の端のx=aとなる点は、左右の近傍の点の集合の真ん中では無いので、微分可能では無い。
それにより、変数xの閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)であっても、微分可能な変数xの値の範囲は開区間(a<x<b)になってしまいます。
(注意2)
この定義における「全ての実数のx」の意味は、他の制限、例えば関数の変数の定義域を定めて定義域外の変数に関して関数を考え無い事にしても、その制限に制約されずに定義される全ての実数xを意味します。
例えば、関数f(x)が有理数の関数であり無理数の関数とは定義されていない場合は、無理数の関数値が存在しないので、傾きAが計算できず、その関数f(x)は微分不可能です。
(注意2の補足その1)
なぜ、変数xが有理数のみの関数が微分不可能になるように「微分可能」の定義をしたかという理由は、以下の事情があるためと考えられます。
ある関数f(x)の定義を、
変数xの値が無理数である場合における関数値f(x)=1とし、
変数xの値が有理数である場合の関数値f(x)=0とする関数f(x)が定義できます。
その関数f(x)は明らかに微分不可能です。
そういうように微分不可能になるのに、変数xの値が有理数の場合に値f(x)が定義されている関数f(x)を微分可能であると定義してしまうと、その関数の変数xが無理数の場合の関数値も考えると微分不可能になってしまい、関数f(x)が微分可能になったり不可能になったり結論が安定しない問題を生じます。
そのような問題が起きないために、変数xの値が無理数の場合に関数値f(x)が定義されていない関数は微分不可能になるように定義したと考えます。
(注意2の補足その2)
連続性は実数まで考えることで正しく定義できる。微分する関数は連続関数であると定義する。そのため、微分可能な関数は、変数xの実数の範囲で定義されます。その微分可能な関数の変数xの値として有理数の値のみしか扱わず無理数の値を全く意識しない場合でも、微分可能な関数は無理数でも定義されている。そういうバックグラウンドを微分可能な関数が持っていると考えます。
(2)
x0の近傍の全ての実数のうちのx0以外の実数xをどの様に選んでも、点(x,f(x))と点(x0,f(x0))を結んだ線分の傾きが、実数xのどの様な選び方でも、漏れなく、同じ有限の値に収束する(例えば、その全ての傾きの値が、確固として同じ有限の値 lim から微小な値 ε 以内の誤差の値に収まる)ならば、
その確固として同じ有限の値の傾きlimが微分係数である。
(3)
また、そのグラフの点を結んだ線分の傾きが一定の、有限の値の傾きに収束しないならば(無限大の傾きもダメ)、微分不可能である。
(4)
また、x0から微小な値 δ 以内にある全ての実数xに対してf(x)が定義されていなければ、x0で微分不可能である。
(4-1)
例えば、関数f(x)の変数xの定義域(a≦x≦b)の定義域の境界点 a では、
aから微小な値 δ 以内の実数の領域の半分が関数f(x)の定義域(a≦x≦b)からはみ出してしまい、その領域が定義域内に収まっていないので、定義域の境界点aでは関数f(x)は微分不可能となってしまいます。
しかし、大学数学では、変数xの閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)の微分は、端点aでは、片側微分があるならば微分可能であると、定義を修正しています。
すなわち、大学生になると、微分可能の第2の定義によって、関数F(x)の端点(x=a)の微分係数をF(x)の片側微分係数で定義します。つまり、関数f(x)の変数xの定義域が、
a≦x≦b
というように定義域が領域の境界点aやbを含む場合は、
関数f(x)が端点で微分可能になるように、微分可能の定義を修正しています。
これについては、後で、「微分可能の定義の拡張」で説明します。
一方で、 関数f(x)の変数xの定義域が、
a<x<b
というように定義域が領域の境界点を含まない開放された領域(開区間)である場合は、
微分可能の定義を修正しないでも、
関数f(x)が微分可能になる変数xの範囲は、
a<x<b
になり、定義域と同じ範囲が微分可能になるという、
面白い事が起きています。
---------(言い換え終わり)-----------
(補足1)
「微分可能」という言葉は、高校3年の数Ⅲで習いますが、高校2年で微分係数を学ぶ時に直ぐ学ぶ方が良いと考えます。
なぜなら、微分と積分は、ある変数値で「微分可能」な関数と、ある変数値の近くで「積分可能」な関数を選んで、微分したり積分したりするからです。「微分可能」と「積分可能」という条件が例外的な場合を考えないで良い条件となっていて、その範囲内で考えることで、例外的な場合を考える労力を節約することができるからです。
微分積分の種々の公式の前提条件として、「微分可能」と「積分可能」という条件の範囲内で考えているからです。
そういう前提条件付きで話がされているということを理解して微分積分を学ぶべきだからです。それが教えられないと、微分と積分の話の本当の事情のカヤの外で説明を聞くことになり、微分積分の説明が理解できなくなるからです。
(補足2)
なお、大学数学で学ぶ特殊な関数にδ関数がある。δ関数は超関数と呼ばれる特殊な関数で、(特殊な形の)微分が定義されている。しかし、δ関数は、x=0での値, とx≠0での値が異なり、x=0で連続ではない。すなわち、x=0では連続でないため、その点では、微分可能ではない。
(関数の増減表を書く場合:閉区間の境界での増減)
閉区間で連続な関数の増減は、閉区間の端点での様子は、片側微分で、増加か減少か、片側微分係数が0かが分かります。その片側微分でわかった結果の微分係数を括弧()の中に書いて表現する、 括弧付き表現で解答します。
上の増減表の場合では、括弧()付きの値を表に書かないと、どの様なグラフであるかが分からなくなります。
------微分可能の定義の拡張について--------------------
先に示した関数f(x)の微分可能の定義は、例えばa<x<bという開区間内の点xのみでの微分可能の定義です。a≦x≦bという閉区間の端点のx=aにも厳密に定義を適用すると、区間の端点では”微分不可能”であるという結論を導く定義になっています。
しかし、その適用は誤りです。大学生以上になると、閉区間の端点での微分可能が以下の様に定義されます。
(区間の端での微分可能の定義)
閉区間で定義された関数F(x)=xの区間の端では、
大学生以上では、片側微分係数が存在すれば、
その片側微分係数を、閉区間の端点での微分係数であると微分の定義を拡張して定義しています。
微分の定義を拡張するのは、以下の事情もあります。
(関数の連続性については区間の端での連続性が定義されている)
閉区間で連続する連続関数については、その端点を除いた区間で関数が連続であって、閉区間の端点で片側連続であれば、端点を含めた閉区間で関数が連続であるという様に、関数の連続性の概念が拡張されています。
関数の微分可能の定義も、同様に微分可能の判別が閉区間の端点でも行えるように拡張されると便利です。
特に、閉区間の端点で微分ができない場合は、以下の問題を生じます。 例えば、変数xが閉区間[a,b]で定義されている関数f(x)を考えます。その関数f(x)を、閉区間[a,x]で積分した関数F(x)-F(a)を作ります。その関数F(x)がx=aでは微分係数が計算できないことになります。そうすると、関数F(x)を微分することでは、x=aでは関数f(x)が求められない事になってしまいます。そのように関数f(x)とF(x)とが、x=aでは、積分による対応はできるのに、微分による対応は出来ないという問題を生じます。
微分と積分とでは、関数の対応関係が異なってしまうアンバランスを生じるという問題があります。
そのため、大学生以上では、以下の、拡張された微分の定義が使われます。
(拡張された微分の定義)
関数F(x)の微分を閉区間の端でも有効にする拡張された定義が、大阪大学の教授が書いた「微分積分学」(難波誠)の、44ページに記載されています。
「閉区間の端点で関数F(x)が片側微分可能であれば、その片側微分を端点での微分係数と定義しています」
閉区間a≦x≦bでの端点x=aとx=bでの微分係数が以下の式で定義されています。
(1)端点b=x0におけるf(x) の微分係数は:
h<0について、
で定義される左側微分係数(left-hand derivative )
を端点bの微分係数と定義します。
(2)端点a=x0におけるf(x) の微分係数は:
h>0について、
で定義される右側微分係数(right-hand derivative)
を端点aの微分係数と定義します。
この、閉区間の端点で、片側微分係数が存在すれば、端点でも微分可能とする拡張された定義は、数学者の藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」の時代からの定義であって確定して受け入れられている定義です。
閉区間で1つながりに連続な関数F(x)を閉区間の端点で微分可能とする拡張された微分の定義が、
小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」の112ページにも記載されています。
「閉区間の端点で関数F(x)が片側微分可能であれば、その片側微分を端点での微分係数と定義しています」
この微分の定義「閉区間の端点では、関数F(x)の微分を片側微分係数で定義する」は大学生以上で使われています。
(不定積分との関係)
0≦x≦2という閉区間の定義域でのみ定義され、その定義域内で常にf(x)=1となる関数f(x)を考える。
f(x)の不定積分F(x)の1つは、
F(x)=x
です。
この様な、F(x)の微分によって大部分のf(x)が再現できるという確認ができた不定積分F(x)が、閉区間の端でも、この定義の片側微分によりf(0)=1も再現できます。
そのため、この不定積分F(x)=xが原始関数であるという説明がされています。
この閉区間での端点の微分の定義をすると連続関数f(x)の不定積分F(x)から逆算してf(x)を計算する計算手順が楽になるので、
この微分の定義
「端点で関数F(x)の微分を片側微分係数で定義する」
は大学生以上で使われています。
------微分可能の定義の拡張の考察おわり------------------
【導関数の定義】
関数f(x) が,実数のある区間 I の各点で微分可能(有限の傾きを持つ)のとき
f(x) は区間 I で微分可能(differentiable on I) であるといいます.
この場合,実数の区間 I の各点にそこでの微分係数を対応させることにより定まる関数を
f(x) の導関数(derivative) といい,
であらわします。
また,関数f(x) の導関数を求めることを微分する(differentiate) といいます.
また、xの関数f(x)=yの微分(導関数)を、y’とも書きます。
(補足3)
ここで、以下の関数の微分係数f’(1)を求める場合を考えます。
この極限に使う変数h+1をxにして、以下の様に書いたらどうでしょうか。
この式も、間違いとは言えないと思いますが、
分母の(x-1)=hが正しく導入できずに、分母をxにしてしまうかもしれない、気持ち悪さがあります。
また、この式では無く、x→0の場合に微分を求める場合は、この式の場合に(x-1)=hを正しく導入できないで分母をxにしてしまう、間違った計算ルールを覚えて計算したのか、ルールを間違えていないのかが採点者に判別できない、気持ちの悪さがあります。
そのため、試験問題で微分を極限で求める場合に、hを使わないでxを使うと減点される可能性が高いと考えます。
(接線の定義)
連続なグラフ上に2点A,Bを取って、その2点をその間の1点のCに無限に近づけた時に、その2点A,Bを通る直線が1つの直線に収束する場合に、その直線を、そのグラフの、点Cにおける接線と呼びます。
(注意)グラフの不連続点においては、その点における接線は考え無いことにする。その不連続点に接する直線があるかもしれないが、その点における「接線」については考え無いことにする。
(接線の定義の言い換え)
(1) XY平面上のY=f(x)であらわすグラフの、X=X0となる1点Cにおいて、
微分係数f’(X0)が存在するとき、その点Cを通り、傾きf’(X0)を持つ直線が点Cにおける接線である。
(2) その微分係数f’(X0)が存在しない(無限大になる)場合には:
そのグラフを、YX平面上のX=g(Y)というグラフとみなして考える。そう考えた場合に、
そのグラフ上の1点C(X0,Y0)において、微分係数dx/dY=g’(Y0)が存在するとき(この場合は、g’(Y0)=0になると思うが)、その点Cを通り、YX平面での傾きdX/dY=g’(Y0)を持つ直線が点Cにおける接線である。
(3) 微分係数f’(X0)が存在せず、微分係数g’(Y0)も存在しない場合、その点Cにおける「接線」については考え無いことにする。その点Cでグラフに接する直線はあるかもしれないが、その点における「接線」は考え無いことにする。
(補足4)
「関数が x0 で微分可能(有限の値の確定した値の微分係数が存在する)」
という意味は、
「関数が、その変数 x のその値 x0 に限って、その変数 x で微分可能であれば良く、その変数 x のその他の値での関数の微分可能性は関係しない」
という意味です。
(補足5)
df/dx=∞
の場合は、傾きが有限で無いので、
変数xで微分可能ではありません。
df/dx=無限大
という関係が存在しても、
「微分係数(df/dx)が存在しない」
とも言われ、微分不可能です。
それは、
x=0において、
関数f(x)=1/x
の値が無限大という関係が存在しても、
「x=0において関数値1/xが存在しない」
と言うのと同じ意味です。
下図のグラフの関数は、x=0となるO点では傾きが無限大なのでx=0では変数xによる微分係数が存在せず、変数xで微分不可能です。
なお、このグラフは、O点でX=0という直線と接します。
それは、このグラフの座標(変数)を変換して、Y座標値を変数であるとみなし、グラフのX座標値を、関数値とみなせば、グラフの微分係数(dX/dY)=0は存在するので、変数Yによるその微分係数で接線X=0が定められるからです。
すなわち、このグラフのYを与えるxの関数はx=0でYがxで微分不可能ですが、この関数の逆関数の、xを与えるYの関数は、変数としてのYの全ての定義域でxがYで微分可能です。
このように、座標系を回転させる座標変換(変数変換の一種とも言える)によって角度を変えて見ると、ある変数Xでは微分不能であった点が、他の変数Yでは微分可能に変わることがあります。
(注意)
このグラフの関数は、x=0で微分不可能ですが、以下の性質は持っています。
すなわち、
Δx→0の場合にΔy→0となる性質は持っています。
そして、このグラフは、
x1<x2の場合にf(x1)<f(x2)となる、単調増加の性質は持っています。
(注意おわり)
「微分可能」を定めた意味は、ある制限条件を定めて、その「制限条件」を外れた関数については”考えないこと”にするのが、「微分可能」という制限条件を定めたた本当の理由だと思います。
以下のグラフの関数については:
このグラフには、X=0の点に接する「接線」が存在しませんが、
その「存在しない」の本当の意味は、
X=0においては微分係数が存在しないので、X=0では「接線のことを考えないことにした」のです。
その影響を受けて、このグラフにおける、X=0で接する線については「接線では無い」と言われるようになったのだと思います。
「接線が無い」のでは無く、「微分不可能な点では接線を考えないことにした」だけなのですが、、、
実際、以下のグラフでは、X=0での微分係数が∞になり微分不可能な曲線の点にY軸に平行な接線が接する。
その場合に、その変数Xで微分不可能な点において、「接線が無い」のではなく「接線を考え無いことにした」ことが明らかです。
また、上のグラフは、x=0の点で変数xで微分不可能です。ところがx=0の点で滑らかにつながっています。
微分のごまかし説明で、「微分可能性の定義は、滑らかにグラフがつながる点が微分可能な点である」というごまかし説明が流布されていますが、その定義は間違いですので気をつけてください。
《下図に各種の関数の集合の包含関係をまとめた》
----(滑らかなグラフと微分可能性との関係)-----
滑らかなグラフと微分可能なグラフは、次の1点のみの差がありますので、その1点のみの差を覚えておきましょう。
滑らかなグラフY=f(x)のうち、傾きdY/dxが無限大になる変数x=x0 の点では、そのグラフの関数f(x)は微分不可能です。それ以外の点では微分可能です。
また、滑らかなグラフでは、その傾きdY/dxが無限大になる点も含む全てのグラフが滑らかに繋がる点で接線が引けます。
----------------------------------------------------
また、Yを変数とした、グラフの、変数Yによる微分係数(dx/dY)は存在し、変数Yによっては微分可能ですが、それが微分可能であっても、変数xによる微分係数(dY/dx)が存在せず、変数xで微分不可能であることに変わりはありません。
(メモ知識)
以下の2つのグラフの関数は、いずれも、x→0の極限で、微分係数(dY/dX)が無限大に発散し、x=0では微分不可能です。

(メモおわり)
【右側微分係数と左側微分係数】
なお、
f(x) がx0 で微分可能でなくても、
h<0について、
または、
h>0について、
が存在することがあります.
下の図のような場合です。
その場合,
最初の値を左側微分係数(left-hand derivative ) と いい,
で表わし,
後の値を右側微分係数(right-hand derivative) といい,
で表わします.
微分可能の定義より,
が共に存在し,かつ両者が等しいとき に限りf(x) はx = x0 で微分可能となります。
------------(補足6)--------------------------
しかし、右側微分係数と左側微分係数が一致しなければ、その点では微分可能では無い(微分係数が存在しない)という微分可能の第1の定義には、以下のような違和感があります。すなわち、右側微分係数も左側微分係数も存在するのに、両者が一致しないからといって、その点を微分不可能と定義して良いのだろうか?と感じる違和感があるのです。
例えば、以下の図のグラフを考えてみます。
このグラフのx=0でのグラフの傾きは2つありますが、そのx=0での点で微分不可能と言うのは不適切だと考えます。なぜなら、そもそも、このグラフは、1つのxの値に対して2つのyの値を対応させている2価関数です。2つのyの値があるので、当然に2つの微分係数があります。その2つの微分係数がたまたま同じ値のyの点で現れたのがx=0の点であるというだけです。また、この2価関数を、xもyも、そして(x,y)の原点からの距離rを角度θの1価の関数と考えると、x=0での2つの傾き(dy/dx)は、θ=π/4の場合と、θ=-π/4の場合と、の2つの異なるθの場合における傾きと考えられます。そういう2つの微分係数が同じ(x,y)の点であらわれるからと言って微分不可能であると言う事はできません。
----補足6おわり----------------------
《関数の連続を前提にした、とある定理》
(とある定理)「ある点での関数の微分可能性を調べる場合に、
その点でその関数が連続である場合は、
微分係数の左側極限(真正の極限では無い)によっても左側微分係数を求めることができ、
微分係数の右側極限(真正の極限では無い)によっても右側微分係数を求めることができ、
微分係数の左側極限と微分係数の右側極限によって、微分可能性を調べることができる。」(とある定理おわり)
すなわち、左側微分係数を計算するのが面倒な場合:
x<x0 における微分係数が存在し、しかも関数f(x)がx0で連続な場合は:
と計算でき、x<x0 の微分係数の左側極限(真正の極限では無い)によって左側微分係数を求めることもできます。
右側微分係数についても:
x>x0 における微分係数が存在し、しかも関数f(x)がx0で連続な場合は:
と計算でき、x>x0 の微分係数の右側極限(真正の極限では無い)によって右側微分係数を求めることもできます。
ただし、関数f(x)がx0 で連続でない場合は、例えば下図のような場合は:
x=x0≡0 の左側微分係数は、-∞ですが、
x<0の関数f(x)のx<0における微分係数f’(x)は1であり、
x→0-
の極限でも、1になりますので、
x0が不連続点である場合に、上の「とある定理」を使うと(定理の適用違反ですが)、
x=x0≡0 の左側微分係数が1であるとしてしまい、
答えを間違えます。
このように、微分するには、先ず、その点で関数が連続であることを調べる確認作業を欠かしてはいけません。その確認の後に、この「とある定理」を使ってください。
(注意)
関数の変数xの値毎に、関数が微分可能か可能でないかが定義されています。
関数f(x)が変数xの値x0において微分可能の場合に、
関数f(x)が初等関数などの通常の関数の場合は、
Δyの誤差が以下の式であらわせます。
----ビッグオー O(Δx2)の 定義--------
ここで、O(Δx2)は、以下のように定義されます。
x=x0+Δxとする絶対値が十分小さいΔxに対して、
ある定数Mがあって、
|Δy-(df/dx)Δx| ≦ MΔxμ
が成り立つとき、
|Δy-(df/dx)Δx|はオーダーμの無限小であると言い、
Δy-(df/dx)Δx=O(Δxμ)とあらわす。
つまり、O(Δx2)は、MのΔx2倍程度の誤差をあらわす誤差関数です。(ΔX=0の場合は、O(0)=0と定義する)
Δxが0に近づくと、誤差O(Δx2)は、Δxよりも更に急速にMのΔx2倍のオーダー(概算値)で0に近づくということをあらわしています。
----(定義おわり)---------------
全ての関数について厳密に成り立つ関係としては:
関数f(x)が変数xのある値xにおいて微分可能であれば、Δxが小さくなればなる程、Δyの誤差が、MのΔx倍よりも急速に小さくなる誤差関数(スモールオー)で表した以下の式が成り立っています。
スモールオー o(Δx)の定義は、上の極限の式であらわされ、Δxよりも急速に小さくなる誤差関数です。(ΔX=0の場合は、o(0)=0と定義する)
Δxが小さくなればなる程、Δyの誤差o(Δx)が、MのΔx倍よりも急速に小さくなるので、Δxが十分小さいと考えれば、誤差が十分小さくなり、以下の近似式がいっそう正確に成り立つようになります。
そのため、Δyを上の式であらわして微分を計算して良いです。
【微分不可能が微分可能に変わる例】
(注意1)関数の変数を変換すると微分不可能な点が微分可能な点に変わることがある。
下図のグラフの関数は、O点では傾きが無限大なのでxで微分不可能です。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
この変数tで元の関数をあらわすと以下のグラフになります。
このグラフはO点で、tで微分可能です。
このように関数の変数を変換する、変数xでは微分不可能だった関数の点が、変数tでは微分可能になる、ということが起こり得ます。
という関係があります。
有限の微分係数が存在する(微分可能)という状態は、変数を変換すると変わることがあります。
それは、微分する変数に応じる「微分可能」という条件が、
いわば、
「式を0で割り算する計算をしてはいけない」
という計算の縛りと似た意味を持つことを意味しています。
(注意2)関数の変数を変換すると微分不可能な点が微分可能な点に変わることがあるもう1つの例を考える。
下図のグラフの関数は、O点では、左側微分係数と右側微分係数が異なるのでxで微分不可能です。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
この変数tで元の関数をあらわすと以下のグラフになります。
このグラフはO点で、tで微分可能です。
このように関数の変数を変換すると、変数xでは微分不可能だった関数の点が、変数tでは微分可能になる、ということが起こり得ます。
(注意3)関数の変数を変換すると、接する2つグラフが接さない2つのグラフに変換される例を考える。
下の2つの関数のグラフは、O点で同じ微分係数=0を持ち、O点で接しています。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
(この関数のグラフは、t=0の点での微分係数が無限大になってしまい、t=0では微分可能ではありません)
この変数tで元の2つの関数をあらわすと以下の2つのグラフになります。
元の2つのグラフの変数xを変数tに変換した2つのグラフは、O点で変数tで微分すると異なる微分係数を持ち、O点で接さず交差しています。
変数を変換すると、このように、互いに接する2つのグラフが、接触する点での微分係数が異なる2つのグラフに変わってしまうことがあることに気をつけましょう。
すなわち、「2つの接するグラフが接点において等しい微分係数を持つ」ことが、グラフの座標変換によって変わってしまい2つのグラフの接触点での微分係数が等しく無くなることが有り得ます。
その様なおかしな事が起こる場合は、変数のその値で微分可能では無い関数を使って変数を変換すると生じ得ます。おかしな事が起こらないようにする1つの十分条件として、変数変換に使う関数を、変数のその値で「微分可能」な関数を使えば、変数がその値の部分でのグラフにはおかしな事が起こりません。
「微分可能」は、このようにおかしな事が起こらないようにする十分条件なのです。これが、「微分可能」と「微分不可能」を区別する意味だと考えます。
この「微分可能」によって、自然な直感で想像できる事がどのようにして生じ得るかの答えは、「合成関数の微分の公式」によって明らかにされますので、それまで地道に勉強を進めて欲しいと思います。
(交差している2つのグラフが、変数変換すると互いに接する2つのグラフに変わる例)
上図のように、変数tの関数f(t)とg(t)との2つの関数値をY=f(t)、及びY=g(t)とする。
f(t)=t
g(t)=t/2
とする。 この場合に、上図のように、2つのグラフが、tY座標平面上では互いに交差しているだけで、接していない。
このグラフの変数tを以下のグラフの関数であらわす媒介変数xを考える。
変数tをこのグラフの関数であらわす媒介変数Xを使うと、
XY平面上で先の2つのグラフをあらわすと以下の図の様になる。
x≧0の場合に:
関数f(t)=x2
関数g(t)=x2/2
になる。
この様にXY座標平面上では、互いに接する2つのグラフに変換されてしまった。
すなわち、接さずに単に交差しているだけの2つのグラフが、互い接するグラフに変わってしまった。
(行なって良い変数変換の条件)
tY座標平面上の2つのグラフがある変数値において接するか否かを調べている時に、そのように変わってしまわないようにするための、行なって良い変数tの媒介変数xへの変数変換は、その2つのグラフが交差する点の位置の変数値において:
(A)
dt/dx ≠ 0
となることが必要です。
(B)
また、その関数が”微分可能”であることも必要で、すなわち、その2つのグラフが交差する点の位置の変数値において:
dt/dx ≠ ±∞
も必要です。
なお、変数を変換する関数t=m(x)が、
dm(x)/dx≠0となるxの連結区間では、
m(x)は単調増加関数か単調減少関数になります。
その区間の単調増加か単調減少な関数t=m(x)には逆関数x=p(t)が存在します。
特に、
dt/dx ≠ 0,
dt/dx ≠ ±∞,
が成り立つ場合には、
逆関数の微分の公式も成り立ちます。
この2つの条件を満足する関数t=m(x)で変数変換をするならば、グラフの所定の点での「微分可能」または「微分不可能」というグラフの性質が変数変換の後でも同じに維持されます。
例えば、t=m(x)=log(x)という関数は、X=0以外の点では、この2つの条件を満足します。
そのため、この関数t=m(x)を使って変数変換するならば、X=0以外の点では、「微分可能」と「微分不可能」という性質が変わりません。
(行なって良い変数変換の使用例)
以下の式1であらわされるグラフを考えます。
Y=xa (式1) (定数 a は所定の実数)
この式1であらわされるグラフは、
グラフが滑らかである大部分の変数値xにおいて、
傾きが∞にならない点で、微分可能です。
この式1のグラフの微分可能性は、以下の様に変数変換して調べることもできます。
この式1を関数log(x)で変換すると、
log(Y)=a*log(X) (式2)
に変換されます。
この式2を
Z=log(Y) (Z>0)
t=log(X) (t>0)
で変数変換すると、
Z=a*t (式3) (ただし、Z>0,t>0)
が得られます。
この式3であらわされるグラフは、元の変数であらわされたグラフと、「微分可能」と「微分不可能」という性質が変わりません。
式3のグラフは「微分可能」ですので、元の式1であらわされたグラフも「微分可能」であることがわかります。
(行なって良い変数変換に関する注意)
「微分可能性」の性質を維持する変数変換の条件は、以上で説明した通りですが、その条件を満足していなくても、式を自由に関数で変換して、関数の微分係数の計算式を導きだして良いのです。0を0で割り算するような計算ルールに違反するような計算をせず正しく微分係数の計算式を導き出せれば、その計算式が得られたことが、その関数が「微分可能」であることの証明になります。
ただし、上の条件を満足せずに、微分係数の計算式を導き出せた場合でも、以下の場合には「微分可能」にはなりませんので注意が必要です。
(1)関数f(x)が、x≧x0 と、x<x0 とで異なる式で定義されていて、x<x0 でのf’(x)の、x→x0 における値と、x>x0 でのf’(x)の、x→x0 における値が異なる場合、変数xの範囲のx0 ーδ<x <x0 +δ の範囲における微分係数の値が1つに確定しないので、x0 で微分不可能です。
(2)このように、微分可能性を、微分係数の計算式の存在によって判定しようとする場合には、変数xの範囲のx0 ーδ<x <x0 +δ において全ての関数値f(x)をしらべることができるか否かをチェックして判定するよう注意してください。
例題2.4
f(x) = xn (n 整数) を微分してみましょう.
となります。
(解答おわり)
が得られました。
次に、以下の微分も計算してみます。
この図形を直線y=xに関して折り返して考えます。
こうして、
が得られました。
(微分の式の前提条件:関数が存在すること)
微分をあらわす式:
(dy/dx)は関数f(x)の導関数をあらわす式です。
そのため、
(dy/dx)=(df(x)/dx)
であり、変数yを微分で使う場合には、
y=f(x)とあらわす関数f(x)が必ず存在することが、変数yを使う前提条件にあります。
関数f(x)が必ず存在するということは、変数xに対して、必ず1つの値のy=f(x)が定まる関係(規則)が、変わらず、存在するということです。
(関数が存在しない例)
以下の関数f(x)で:
(df(x)/dx)=0となっているグラフの部分(y=0の部分)については、以下の逆関数g(y)のグラフの様に:
y=0となっているグラフの部分では、逆関数g(y)が存在しない。 そして、g(y)のy=0での右側極限と左側極限が一致しない。そのため、Δy→0の場合にΔx→0とはならない。
----関数が存在しない例おわり------------------
微分の式は、定まった関数であらわされる関係が必ず存在する変数yとxその他の媒介変数の間の関係をあらわす式です。
微分の計算で使う全ての変数yやxやその他の媒介変数同士は、必ず、その変数を他の変数であらわす不変な関数で結ばれていることが前提にあります。
その関数はどの式であっても良いですが、計算の途中で変化することが無い、いつも変わらない関係式であることが微分の計算の前提になっています。
(微分可能な関数を選んで微分すること)
下図のグラフの関数はでこぼこしていて、でこぼこがあらゆる細部にまで在り、どの有理数のxの位置においても微分不可能な関数の例です。
また、微分不可能な関数F(x)として、連続関数であり、かつ、あらゆるところで微分不可能な関数であるワイエルシュトラス関数F(x)などもあります。
この図の関数のように、関数が微分不可能な変数の値を判定して、変数の範囲(定義域)から除外するために、「微分」の定義を使って関数の変数を選別して、その変数の範囲の関数を微分計算の対象にします。
実際は、微分不可能な関数は、警戒しなければならないほどに多く存在するわけでは無く。数学で学んで来た、ほとんど大部分の初等関数は微分可能な関数です。
また、上のグラフのようf(x)が微分不可能な変数の値(有理数)が無限にある関数f(x)であっても、積分はできます。
(ただし、あらゆるところで微分不可能な関数F(x)については、その関数F(x)を微分した結果の片りんさえも存在しないので、その関数F(x)は何かの関数f(x)の積分では得られません。)
元の関数f(x)が連続関数等の、関数の極限が存在する関数の場合は、その関数f(x)を積分して得た関数F(x)は微分可能な関数になります。こうして、極限が存在する関数f(x)の集合の要素の各関数f(x)を積分して関数F(x)の集合を作れば、その関数の集合の要素の各関数F(x)は、どれも微分可能な関数であることが保証されます。
(「リーマン積分可能」の定義)
「微分積分学入門」(横田 壽)の124ページから125ページに「リーマン積分可能」の定義が書いてあります:
(この本は書店で購入できます。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
ここではドイツの数学者G.F.B. Riemann (1826-1917) によって示されたRiemann 積分につ いて学んでいきます.リーマン積分による「積分可能」の定義は、全ての種類の「積分可能」の定義の基礎になっています。
f(x) は閉区間[a, b] で定義されているとします.この閉区間[a, b] を次のような点xi(i = 1, 2, . . . , n) でn 個の小区間に分割します.
(a = x0 < x1 < x2 < · · · < xi < · · · < xn = b)
この分割をΔ で表わし, Δxi = xi − xi−1 (i = 1, 2, . . . , n) のうちで最も大きい値を|Δ| で 表わします.
いま,それぞれの小区間[xi−1, xi] のなかに任意の点ξi をとり,Riemann 和 (Riemann sum) とよばれる次の和を考えます.
このとき、
となる実数S が存在するならば,このS をf(x) の定積分(definite integral) といい, f(x) は閉区間[a, b] で積分可能(integrable) であるといいます.また,このS を次のように表わします.
つまり関数f(x) が閉区間[a, b] で積分可能であるということは,分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まるということです.
この定義に従い、関数の積分可能性を以下の様にして調べることができます。
先ず小さな閉区間[a, b] を定めて、
その区間の小区間への分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まる(積分可能)か否かを調べることができます。
【積分が不可能な関数】
下のグラフの関数f(x)のように、どの位置においても関数の極限が存在しない関数もあり得ます。
例えば、
xが有理数の場合にf(x)=0であって、
xが無理数の場合のf(x)=1
という、極限が存在しない関数f(x)などです。
そういう、極限が存在しない関数f(x)を積分して関数F(x)を得た場合(もし積分できた場合)、その積分により得られた関数F(x)は微分可能だろうか。
そもそも、微分の計算は極限を求める計算なので、その関数f(x)が積分できても、その積分した関数F(x)を微分した場合に、元の関数f(x)は(極限値が存在しないので)、微分によっては得られないと考えます。
この関数f(x)の変数x=x1からx=x2までの変数xの閉区間をn等分した小区間を作り、その各小区間毎にf(x)の値f(ξ)を求めて、その値の和で積分します。
(1)その際に、 変数x=ξが全て有理数なら、f(ξ)=0になり、積分結果は0になります。
(2)一方、変数x=ξが全て無理数√2の有理数倍なら、f(ξ)=1になり、積分結果は(x2-x1)になります。
(3)小区間内の変数xの点ξの選び方によってf(ξ)の和による積分結果が変わるような計算の値は定かでは無いので、その様な関数f(x)は積分することができません。
なお、以下の関数F(x)は微分可能ですが、それを微分して得た導関数f(x)に不連続点(微分不可能な点)があります。
x≠0の場合:
x=0の場合: F(0)=0,
この関数F(x)はx≠0の場合に微分可能で、
その導関数f(x)は:
になり、xが0に近づくとー1と1の間を振動します。
この導関数が含むcos(1/x)の関数が以下のグラフであらわす形の関数になるからです。
X=0の場合にも、F(x)は微分可能で:
というように、0になります。
そのため、関数F(x)は、全てのxの値で微分可能です。
しかし、関数F(x)の導関数f(x)は、x=0で値f(0)=0を持ちますが、x=0で不連続です。
このF(x)のように、微分すると不連続点を持つ関数f(x)になるが、F(x)自体は、全ての変数値で微分が可能という関数F(x)があるのです。
なお、関数f(x)が変数xのある値で不連続ならば、必ずその点でf(x)は微分不可能になります。これは、「関数が変数xのある値で微分可能ならば、必ずその点で連続である」と言う定理の対偶として成り立っています。
このように、微分積分学では、あらゆる関数に微分積分を行う理論を作ろうとすると、いろいろな難しい問題があることがわかりました。
微分積分学で、難しい問題が生じない関数の範囲を把握して、その範囲内で微分積分の計算をすることで、応用上で微分積分を使い易くできます。
そのため、使い易い関数として、極限が存在し、かつ、変数xの実数のすき間がない1つながりの区間内で連続な「連続関数」 を主に扱う対象にする。また、「微分可能性」で関数の変数の定義域を微分可能な区間に制限する。そのように、扱う関数を制限します。その関数の変数xの区間内で、その関数に関して成り立つ法則を把握して、種々の公式を導き出して使う。そうすることで微分積分学を最大限に応用できるようになります。
(連続関数を使う利点)
変数xが、閉区間の、
a≦x≦b
で連続な連続関数f(x)の関数については、
(関数の連続性については連続性の定義が拡張されている) で説明したように、閉区間の端点での連続性の定義の修正があります。
また、大学生以上で、閉区間での端点での微分可能の定義を修正することで、
関数f(x)が連続な変数xの範囲で、関数f(x)が微分可能にもなり得るという、微分の概念が使い易くされています。
-----(補足7)----------------
なお、この様に定義の修正をした微分可能の概念を使った定理を証明する場合、少なくとも微分の定義については、その定義の修正も検討して定理を証明する煩わしさを避けるため、微分可能な領域を開区間に限定して、各定理を定義しています。
平均値の定理の記述などで、
「関数が閉区間a≦x≦bで連続であって、開区間a<x<bで微分可能である場合に」
という条件を定めているのは、閉区間の端点での微分可能の定義の修正を考えて定理を証明する煩わしさを避けるため、定理の前提条件をその様に、閉区間で連続で開区間で微分可能と定めています。
--------補足7おわり---------------
こうして、微分積分学は、微分可能な関数と積分可能な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をします。「微分可能」と「積分可能」という制限条件を定め、その制限条件を満足する関数を扱うのが微分積分学だと認識することがとても大切です。
その様に、「微分可能」の制限条件を定めて、その「制限条件」を外れた関数については”考えないこと”にするのが、「微分可能」を定義した本当の理由だと思います。
《下図に各種の関数の集合の包含関係をまとめた》
積分前の関数f(x)と、微分前の関数F(x)との、変数xの一部の定義域での微分積分のあり得る関係が以下の図であらわせます。
(上図で、関数f2(x)は、除去可能な不連続点を除去した関数です。関数F(x)は、関数F(x)の不連続点を除いた変数xの範囲でf(x)の不定積分であるとともに、f2(x)の不定積分でもあります)
「微分可能」な関数と「積分可能」な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をすることが微分積分学の本質です。しかし、その本質を考える礎である一番大切な概念である「微分可能」と「積分可能」を高校2年には教えない。高校3年に至っても「積分可能」の概念を教えていないようです。
しかも、1997年からは、日本の高校の数学IIで面積が無定義に用いられという、数学センスを否定する蛮行が行なわれた。そして、関数f(x)のグラフとx軸で囲まれる領域の面積を,x方向で微分するともとの関数f(x)になり、面積の微分がf(x)となるという本末転倒なことを教えるようになった。
現在の高等学校の教科書は,積分の概念の説明を回避している。
このようなデタラメな教育では、高校生に微分積分が分からないのも無理無いと考えます。
(微分積分の教育方針)
ヨーロッパやアメリカでは、「高校で微分積分を教えるのは、直感にうったえる内容に限られ、正確な微分積分を教えられない」という理由で、微分積分は大学生に教える科目になっています。
日本の大学でも、その欧米の教育に合わせて、初めて学ぶ者に分かるように微分積分を改めて教育しているようです。
大学で使う微分積分の参考書は、高校で教える微分積分の知識を全く知らない学生に理解できるように書かれています。
しかも、大学生向けの微分積分の参考書の方が、日本の高校生向けの微分積分の参考書よりやさしく分かり易い。
高校の微分積分を勉強するなら、先ず、大学生向けの微分積分の参考書を読むことを推薦します。高校の微分・積分の教科書は分かりにくいだけで無く、間違いも含まれています。読まない方が良いのではないかと考えます。
大学生向けの参考書の、
「微分積分学入門」(横田 壽)
を読んでみることをお勧めします。
(この本は書店で購入できます。)
(しかし、同じ著者の書いた高校生向けの参考書「確実に身につく微分積分(2012年)」の1版は、内容が劣化しているのでお勧めできません。大学生向けの本物の知識の参考書「微分積分学入門(2004年)」を読んでください。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
「微分積分学入門」(横田 壽)の読み方は、 66ページから始まる2章「微分法」の以前のページは斜め読みして、何が書いてあるらしいかを漠然と把握しておいて、2章「微分法」以降を精読することをお勧めします。読んでいるうちに知らない関数や概念が出てきたら、66ページ以前に書いてありますので、探して、その部分を読んで理解するように勉強してください。
リンク:
高校数学の目次
▽はじめに
▽ 微分とは何か
▽定義の言い換え
▽関数の増減表
▽微分可能の定義の拡張=区間の端での微分可能の定義
▽接線の定義
▽右側微分係数と左側微分係数
▽関数の連続を前提にした、とある定理
▽微分不可能が微分可能に変わる例
▽行なって良い変数変換の条件
▽例題2.4
▽微分の式の前提条件:関数が存在すること
▽リーマン積分可能の定義
▽積分が不可能な関数
(はじめに)「微分・積分」の勉強について
高校2年生から、極限・微分・積分の「意味がわからない」「つまらない」「教わる計算方法が正しいと言える理由(証明)がわからない」で数学の学習から脱落する高校2年生が多いらしい。
その脱落の原因は、高校2年の極限・微分・積分の授業では、数学のうたい文句から外れた教育がされるからではないかと考えます。
すなわち、今までは、
「数学は、公式を正しく証明した後にその公式を使う」
と言って来たが、
高校2年生の、極限・微分・積分の授業からは、
「数学は、計算結果さえ合えば良い、途中の経緯は問わない、公式の証明は間違っていても問題視しない」
という教育思想が入り込み、
その思想の行き過ぎを避けるため、
「便利すぎる公式は、それをつかって直ぐ答えが得られてしまうから教えない」
という思想が混ざり、
数学教育に大きな濁りが入り込むので「微分積分がつまらない」となる原因があるのではないかと考えます。
その濁りに押し流され無いため、高校2年生も 公式を厳密に証明して納得してから使う、数学の心に従って極限・微分・積分の学習をして欲しいと考えます。
また、微分積分の正しい情報を与えてくれる、高校2年生が勉強しても、内容がわかり易くて良い微分積分の参考書の「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円 等の正しい情報を与えてくれる参考書を入手して、正しい情報を学習するのが良いと思います。
(微分とは何か)
先ず、微分とは何かを、微分可能のハッキリした定義を知ることで頭を整理しましょう。
微分可能の定義は:
(1)第1の定義の微分可能:
開放された開区間(a<x<b)の関数f(x)でxの右側微分係数と左側微分係数が一致する場合に微分係数が存在し微分可能であるとする定義。
(2)第2の定義の微分可能:
閉区間( a≦x≦b)の関数f(x)の、x=aとx=bとの区間の端点では、片側微分係数があるだけで、微分係数が存在し微分可能であるとする定義。
との2通りの定義があるので要注意です。
(微分積分学の基本定理との関係)
微分積分学の基本定理の根底を支えているのが微分可能の定義です。高校数学に与えられている微分可能の定義は第1の定義だけです。それにより、変数xの閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)であっても、微分可能な変数xの値の範囲は開区間(a<x<b)になってしまいます。そのため、高校数学では、開区間(a<x<b)で定義された関数 f(x)にしか、微分積分学の基本定理が成り立ちません。
一方、大学数学では、変数xが閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)の区間の端点x=a,bでも微分可能が定義されています。そのため、大学数学では、閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)にも微分積分学の基本定理が成り立つと教えられています。
ーー【区間の定義】ーー
「区間」という数学用語は、変数xの数直線上の1つの範囲内の、実数のすき間がない1かたまりの数の集合をあらわす数学用語である。
《神奈川大学》【定義 14.2.4.】
a, b を実数とする. a 以上かつ b 以下の実数をすべて集めた集合を [a, b] と書き, これを閉区 間と呼ぶ.
a より大きくかつ b 未満の実数をすべて集めた集合を (a, b) と書き, これを開区間と呼ぶ.
----定義おわり----
a≦x≦bを満足するxの区間という表現は、a≦x≦bの範囲内の全ての実数xという意味です。
-∞<x<∞という区間もあります。
区間はxの値の範囲を限定するためのa≦x≦bという式とは意味が異なることに注意する必要があります。
(A)「0≦x≦2の区間の変数xで定義された関数f(x)がその区間の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数である」という文では、
f(x)は、0≦x≦2の区間で1つながりに連続した関数f(x)として定義されます。連続関数は、平均値の定理を満足する関数です。。
(B)高校数学での、誤った連続関数の定義
「変数xの0≦x≦2の範囲内の値で関数f(x)が定義されていて、その関数f(x)が定義域の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数である」という高校数学の連続関数の定義では、f(x)は、例えば、
0<x<1で f(x)=0, この定義域内の各点で連続。
1<x<2で f(x)=1, この定義域内の各点で連続。
結局、0≦x≦2の範囲内の全ての定義域の各点で連続という関数も連続関数f(x)にされます。しかし、そのように、すき間をはさんだ2つの区間を合わせた複合区間を定義域とする関数は平均値の定理を満足しない。それは連続関数ではなく、その定義は正しい連続関数の定義ではない。
この例の様に、「区間」という用語は変数xの数直線上の、すき間がない1かたまりの実数の集合をあらわす。変数xの数直線上の「区間」では、その変数xの範囲内に実数のすき間があってはいけない。
区間a≦x≦bが命題の中に記載されている場合は、その範囲内の全ての実数xについて命題を検討する必要があります。被積分関数f(x)が定義されていない変数xの点があっても、その点も、その命題が検討されるべき点の1つです。
「区間」という用語は、特に重要な関数である連続関数の連続性を定義するために必要な、連続関数f(x)の変数xの集合体がいつも持っていなければならない連続性という重要な性質が「区間」という概念を用いてあらわされている。
すなわち、変数xの「区間」の性質で大切なのは、
「区間」のなかに変数xの値が隙間なく存在すること。
つまり所定範囲内での隙間が無い1かたまりの実数の集合という概念が「区間」という用語で定義されている。
《命題を検討すべき優先順位》
(1)関数f(x)を収める区間:
a≦x≦b(あるいはa<x<b)内の全ての実数x。
(2)その区間内の座標xにおける点。
(3)その区間内で関数f(x)が定義されている(f(x)の値が存在する)変数xの範囲(xの定義域):
a<x<(b-(a+b)/2) という範囲を定義域とする事や、
その範囲内の有理数のxのみを定義域とする事。
です。
区間について考えるという事は、その区間内の全ての実数の座標xの点を考え、その座標xでf(x)が定義されていない場合でも、その座標xについて考えるという事を意味します。すなわち、関数の微分可能性は、変数xの数直線上の実数が隙間なくつまっている区間を基にして定義される概念であって、関数の定義域を基にして定義される概念ではない。
区間を使って考える場合は、例えば、ある区間内の全ての実数の点のうち、関数f(x)が定義されず関数f(x)が連続で無い(数直線上の)点xについては、「区間内のその点xでf(x)が定義されず関数f(x)がその点xで連続していない」というふうに考えます。xの区間とは、そのようにして、関数の定義域よりも優先して考えるxの数直線上の、実数が隙間なく充填されている範囲の事です。
----------区間の定義終わり-------------
--(連続関数の定義の誤りに注意)---
また、高校で教えている連続関数の定義が間違っていて、それも微分可能の意味を理解できなくする原因になっているので要注意です。
小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」で定義されている連続関数の定義のように、大学では、定義域として、実数を完全に含んで連結している1つながりの「区間」の全ての実数のxで定義されている関数f(x)に限って連続関数を定義しています。
「区間Iで定義された関数f(x)がその定義域の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数であるという」
という表現が正しい連続関数の定義です。
ここで、「区間」という言葉が使われた時点で、それは1つながりの連結区間であって、それは、連続で無い点で分断された領域のことでは無い事に十分に注意する必要があります。
ーー注意のおわり---
関数f(x)であらわされるグラフの傾きは、以下のようにあらわされます。
この傾きは以下に説明する微分によって求めます。
---(定義2.1 「微分積分学入門」(横田 壽)67ページ---
(第1の定義の微分可能)
関数f(x) が、変数xのx0 を含むある開区間(a<x<b)で定義されているとき,極限値
(有限の傾きA)
が存在するならば,
関数f(x) は, x = x0 で微分可能(differentiable) であるといいます.
また,この極限値A を点x0 における微分係数といい,
で表わします.
-----(定義おわり)---------------------------
-----(定義の言い換え)---------------
微分可能の定義を理解するために、以下の様に、自分の言葉で定義を言い換えするのが良いと考えます。
(1)
区間を使った定義なので、
x0に近い(例えばx0から微小な値 δ 以内の誤差の)全ての実数の値の変数x(ただしx0を除外する)を考える。
(注意1)
微分可能の定義には、x0 と、それ以外の値のxとを考えるという条件が必ず入るので(曲線の傾きを求めるには、必ず異なる2点を使う必要がある)、x0以外の全ての実数の点を強制的に調べることを定義に加えている極限の定義と相性が良いので、極限を使って微分可能を定義している。
また、点x=x0でのf(x)の微分可能の定義は、点x=x0だけで定義されるのでは無く、x0の点とその近傍の点との点の集合全体を使って、x0の点でのf(x)の微分可能を定義している。高校数学に与えられている微分可能の定義は第1の定義だけです。
微分可能の第1の定義では、x0の点の左右の近傍の点の集合が存在する必要があり、その点の集合の真ん中の点が微分可能なx0の点です。
関数f(x)を与える点の集合がa≦x≦bの閉区間で定義されている場合に、その区間の端のx=aとなる点は、左右の近傍の点の集合の真ん中では無いので、微分可能では無い。
それにより、変数xの閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)であっても、微分可能な変数xの値の範囲は開区間(a<x<b)になってしまいます。
(注意2)
この定義における「全ての実数のx」の意味は、他の制限、例えば関数の変数の定義域を定めて定義域外の変数に関して関数を考え無い事にしても、その制限に制約されずに定義される全ての実数xを意味します。
例えば、関数f(x)が有理数の関数であり無理数の関数とは定義されていない場合は、無理数の関数値が存在しないので、傾きAが計算できず、その関数f(x)は微分不可能です。
(注意2の補足その1)
なぜ、変数xが有理数のみの関数が微分不可能になるように「微分可能」の定義をしたかという理由は、以下の事情があるためと考えられます。
ある関数f(x)の定義を、
変数xの値が無理数である場合における関数値f(x)=1とし、
変数xの値が有理数である場合の関数値f(x)=0とする関数f(x)が定義できます。
その関数f(x)は明らかに微分不可能です。
そういうように微分不可能になるのに、変数xの値が有理数の場合に値f(x)が定義されている関数f(x)を微分可能であると定義してしまうと、その関数の変数xが無理数の場合の関数値も考えると微分不可能になってしまい、関数f(x)が微分可能になったり不可能になったり結論が安定しない問題を生じます。
そのような問題が起きないために、変数xの値が無理数の場合に関数値f(x)が定義されていない関数は微分不可能になるように定義したと考えます。
(注意2の補足その2)
連続性は実数まで考えることで正しく定義できる。微分する関数は連続関数であると定義する。そのため、微分可能な関数は、変数xの実数の範囲で定義されます。その微分可能な関数の変数xの値として有理数の値のみしか扱わず無理数の値を全く意識しない場合でも、微分可能な関数は無理数でも定義されている。そういうバックグラウンドを微分可能な関数が持っていると考えます。
(2)
x0の近傍の全ての実数のうちのx0以外の実数xをどの様に選んでも、点(x,f(x))と点(x0,f(x0))を結んだ線分の傾きが、実数xのどの様な選び方でも、漏れなく、同じ有限の値に収束する(例えば、その全ての傾きの値が、確固として同じ有限の値 lim から微小な値 ε 以内の誤差の値に収まる)ならば、
その確固として同じ有限の値の傾きlimが微分係数である。
(3)
また、そのグラフの点を結んだ線分の傾きが一定の、有限の値の傾きに収束しないならば(無限大の傾きもダメ)、微分不可能である。
(4)
また、x0から微小な値 δ 以内にある全ての実数xに対してf(x)が定義されていなければ、x0で微分不可能である。
(4-1)
例えば、関数f(x)の変数xの定義域(a≦x≦b)の定義域の境界点 a では、
aから微小な値 δ 以内の実数の領域の半分が関数f(x)の定義域(a≦x≦b)からはみ出してしまい、その領域が定義域内に収まっていないので、定義域の境界点aでは関数f(x)は微分不可能となってしまいます。
しかし、大学数学では、変数xの閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)の微分は、端点aでは、片側微分があるならば微分可能であると、定義を修正しています。
すなわち、大学生になると、微分可能の第2の定義によって、関数F(x)の端点(x=a)の微分係数をF(x)の片側微分係数で定義します。つまり、関数f(x)の変数xの定義域が、
a≦x≦b
というように定義域が領域の境界点aやbを含む場合は、
関数f(x)が端点で微分可能になるように、微分可能の定義を修正しています。
これについては、後で、「微分可能の定義の拡張」で説明します。
一方で、 関数f(x)の変数xの定義域が、
a<x<b
というように定義域が領域の境界点を含まない開放された領域(開区間)である場合は、
微分可能の定義を修正しないでも、
関数f(x)が微分可能になる変数xの範囲は、
a<x<b
になり、定義域と同じ範囲が微分可能になるという、
面白い事が起きています。
---------(言い換え終わり)-----------
(補足1)
「微分可能」という言葉は、高校3年の数Ⅲで習いますが、高校2年で微分係数を学ぶ時に直ぐ学ぶ方が良いと考えます。
なぜなら、微分と積分は、ある変数値で「微分可能」な関数と、ある変数値の近くで「積分可能」な関数を選んで、微分したり積分したりするからです。「微分可能」と「積分可能」という条件が例外的な場合を考えないで良い条件となっていて、その範囲内で考えることで、例外的な場合を考える労力を節約することができるからです。
微分積分の種々の公式の前提条件として、「微分可能」と「積分可能」という条件の範囲内で考えているからです。
そういう前提条件付きで話がされているということを理解して微分積分を学ぶべきだからです。それが教えられないと、微分と積分の話の本当の事情のカヤの外で説明を聞くことになり、微分積分の説明が理解できなくなるからです。
(補足2)
なお、大学数学で学ぶ特殊な関数にδ関数がある。δ関数は超関数と呼ばれる特殊な関数で、(特殊な形の)微分が定義されている。しかし、δ関数は、x=0での値, とx≠0での値が異なり、x=0で連続ではない。すなわち、x=0では連続でないため、その点では、微分可能ではない。
(関数の増減表を書く場合:閉区間の境界での増減)
閉区間で連続な関数の増減は、閉区間の端点での様子は、片側微分で、増加か減少か、片側微分係数が0かが分かります。その片側微分でわかった結果の微分係数を括弧()の中に書いて表現する、 括弧付き表現で解答します。
------微分可能の定義の拡張について--------------------
先に示した関数f(x)の微分可能の定義は、例えばa<x<bという開区間内の点xのみでの微分可能の定義です。a≦x≦bという閉区間の端点のx=aにも厳密に定義を適用すると、区間の端点では”微分不可能”であるという結論を導く定義になっています。
しかし、その適用は誤りです。大学生以上になると、閉区間の端点での微分可能が以下の様に定義されます。
(区間の端での微分可能の定義)
閉区間で定義された関数F(x)=xの区間の端では、
大学生以上では、片側微分係数が存在すれば、
その片側微分係数を、閉区間の端点での微分係数であると微分の定義を拡張して定義しています。
微分の定義を拡張するのは、以下の事情もあります。
(関数の連続性については区間の端での連続性が定義されている)
閉区間で連続する連続関数については、その端点を除いた区間で関数が連続であって、閉区間の端点で片側連続であれば、端点を含めた閉区間で関数が連続であるという様に、関数の連続性の概念が拡張されています。
関数の微分可能の定義も、同様に微分可能の判別が閉区間の端点でも行えるように拡張されると便利です。
特に、閉区間の端点で微分ができない場合は、以下の問題を生じます。 例えば、変数xが閉区間[a,b]で定義されている関数f(x)を考えます。その関数f(x)を、閉区間[a,x]で積分した関数F(x)-F(a)を作ります。その関数F(x)がx=aでは微分係数が計算できないことになります。そうすると、関数F(x)を微分することでは、x=aでは関数f(x)が求められない事になってしまいます。そのように関数f(x)とF(x)とが、x=aでは、積分による対応はできるのに、微分による対応は出来ないという問題を生じます。
微分と積分とでは、関数の対応関係が異なってしまうアンバランスを生じるという問題があります。
そのため、大学生以上では、以下の、拡張された微分の定義が使われます。
(拡張された微分の定義)
関数F(x)の微分を閉区間の端でも有効にする拡張された定義が、大阪大学の教授が書いた「微分積分学」(難波誠)の、44ページに記載されています。
「閉区間の端点で関数F(x)が片側微分可能であれば、その片側微分を端点での微分係数と定義しています」
閉区間a≦x≦bでの端点x=aとx=bでの微分係数が以下の式で定義されています。
(1)端点b=x0におけるf(x) の微分係数は:
h<0について、
で定義される左側微分係数(left-hand derivative )
を端点bの微分係数と定義します。
(2)端点a=x0におけるf(x) の微分係数は:
h>0について、
で定義される右側微分係数(right-hand derivative)
を端点aの微分係数と定義します。
この、閉区間の端点で、片側微分係数が存在すれば、端点でも微分可能とする拡張された定義は、数学者の藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」の時代からの定義であって確定して受け入れられている定義です。
閉区間で1つながりに連続な関数F(x)を閉区間の端点で微分可能とする拡張された微分の定義が、
小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」の112ページにも記載されています。
「閉区間の端点で関数F(x)が片側微分可能であれば、その片側微分を端点での微分係数と定義しています」
この微分の定義「閉区間の端点では、関数F(x)の微分を片側微分係数で定義する」は大学生以上で使われています。
(不定積分との関係)
0≦x≦2という閉区間の定義域でのみ定義され、その定義域内で常にf(x)=1となる関数f(x)を考える。
f(x)の不定積分F(x)の1つは、
F(x)=x
です。
この様な、F(x)の微分によって大部分のf(x)が再現できるという確認ができた不定積分F(x)が、閉区間の端でも、この定義の片側微分によりf(0)=1も再現できます。
そのため、この不定積分F(x)=xが原始関数であるという説明がされています。
この閉区間での端点の微分の定義をすると連続関数f(x)の不定積分F(x)から逆算してf(x)を計算する計算手順が楽になるので、
この微分の定義
「端点で関数F(x)の微分を片側微分係数で定義する」
は大学生以上で使われています。
------微分可能の定義の拡張の考察おわり------------------
【導関数の定義】
関数f(x) が,実数のある区間 I の各点で微分可能(有限の傾きを持つ)のとき
f(x) は区間 I で微分可能(differentiable on I) であるといいます.
この場合,実数の区間 I の各点にそこでの微分係数を対応させることにより定まる関数を
f(x) の導関数(derivative) といい,
であらわします。
また,関数f(x) の導関数を求めることを微分する(differentiate) といいます.
また、xの関数f(x)=yの微分(導関数)を、y’とも書きます。
(補足3)
ここで、以下の関数の微分係数f’(1)を求める場合を考えます。
この極限に使う変数h+1をxにして、以下の様に書いたらどうでしょうか。
この式も、間違いとは言えないと思いますが、
分母の(x-1)=hが正しく導入できずに、分母をxにしてしまうかもしれない、気持ち悪さがあります。
また、この式では無く、x→0の場合に微分を求める場合は、この式の場合に(x-1)=hを正しく導入できないで分母をxにしてしまう、間違った計算ルールを覚えて計算したのか、ルールを間違えていないのかが採点者に判別できない、気持ちの悪さがあります。
そのため、試験問題で微分を極限で求める場合に、hを使わないでxを使うと減点される可能性が高いと考えます。
(接線の定義)
連続なグラフ上に2点A,Bを取って、その2点をその間の1点のCに無限に近づけた時に、その2点A,Bを通る直線が1つの直線に収束する場合に、その直線を、そのグラフの、点Cにおける接線と呼びます。
(注意)グラフの不連続点においては、その点における接線は考え無いことにする。その不連続点に接する直線があるかもしれないが、その点における「接線」については考え無いことにする。
(接線の定義の言い換え)
(1) XY平面上のY=f(x)であらわすグラフの、X=X0となる1点Cにおいて、
微分係数f’(X0)が存在するとき、その点Cを通り、傾きf’(X0)を持つ直線が点Cにおける接線である。
(2) その微分係数f’(X0)が存在しない(無限大になる)場合には:
そのグラフを、YX平面上のX=g(Y)というグラフとみなして考える。そう考えた場合に、
そのグラフ上の1点C(X0,Y0)において、微分係数dx/dY=g’(Y0)が存在するとき(この場合は、g’(Y0)=0になると思うが)、その点Cを通り、YX平面での傾きdX/dY=g’(Y0)を持つ直線が点Cにおける接線である。
(3) 微分係数f’(X0)が存在せず、微分係数g’(Y0)も存在しない場合、その点Cにおける「接線」については考え無いことにする。その点Cでグラフに接する直線はあるかもしれないが、その点における「接線」は考え無いことにする。
(補足4)
「関数が x0 で微分可能(有限の値の確定した値の微分係数が存在する)」
という意味は、
「関数が、その変数 x のその値 x0 に限って、その変数 x で微分可能であれば良く、その変数 x のその他の値での関数の微分可能性は関係しない」
という意味です。
(補足5)
df/dx=∞
の場合は、傾きが有限で無いので、
変数xで微分可能ではありません。
df/dx=無限大
という関係が存在しても、
「微分係数(df/dx)が存在しない」
とも言われ、微分不可能です。
それは、
x=0において、
関数f(x)=1/x
の値が無限大という関係が存在しても、
「x=0において関数値1/xが存在しない」
と言うのと同じ意味です。
下図のグラフの関数は、x=0となるO点では傾きが無限大なのでx=0では変数xによる微分係数が存在せず、変数xで微分不可能です。
なお、このグラフは、O点でX=0という直線と接します。
それは、このグラフの座標(変数)を変換して、Y座標値を変数であるとみなし、グラフのX座標値を、関数値とみなせば、グラフの微分係数(dX/dY)=0は存在するので、変数Yによるその微分係数で接線X=0が定められるからです。
すなわち、このグラフのYを与えるxの関数はx=0でYがxで微分不可能ですが、この関数の逆関数の、xを与えるYの関数は、変数としてのYの全ての定義域でxがYで微分可能です。
このように、座標系を回転させる座標変換(変数変換の一種とも言える)によって角度を変えて見ると、ある変数Xでは微分不能であった点が、他の変数Yでは微分可能に変わることがあります。
(注意)
このグラフの関数は、x=0で微分不可能ですが、以下の性質は持っています。
すなわち、
Δx→0の場合にΔy→0となる性質は持っています。
そして、このグラフは、
x1<x2の場合にf(x1)<f(x2)となる、単調増加の性質は持っています。
(注意おわり)
「微分可能」を定めた意味は、ある制限条件を定めて、その「制限条件」を外れた関数については”考えないこと”にするのが、「微分可能」という制限条件を定めたた本当の理由だと思います。
以下のグラフの関数については:
このグラフには、X=0の点に接する「接線」が存在しませんが、
その「存在しない」の本当の意味は、
X=0においては微分係数が存在しないので、X=0では「接線のことを考えないことにした」のです。
その影響を受けて、このグラフにおける、X=0で接する線については「接線では無い」と言われるようになったのだと思います。
「接線が無い」のでは無く、「微分不可能な点では接線を考えないことにした」だけなのですが、、、
実際、以下のグラフでは、X=0での微分係数が∞になり微分不可能な曲線の点にY軸に平行な接線が接する。
その場合に、その変数Xで微分不可能な点において、「接線が無い」のではなく「接線を考え無いことにした」ことが明らかです。
また、上のグラフは、x=0の点で変数xで微分不可能です。ところがx=0の点で滑らかにつながっています。
微分のごまかし説明で、「微分可能性の定義は、滑らかにグラフがつながる点が微分可能な点である」というごまかし説明が流布されていますが、その定義は間違いですので気をつけてください。
《下図に各種の関数の集合の包含関係をまとめた》
----(滑らかなグラフと微分可能性との関係)-----
滑らかなグラフと微分可能なグラフは、次の1点のみの差がありますので、その1点のみの差を覚えておきましょう。
滑らかなグラフY=f(x)のうち、傾きdY/dxが無限大になる変数x=x0 の点では、そのグラフの関数f(x)は微分不可能です。それ以外の点では微分可能です。
また、滑らかなグラフでは、その傾きdY/dxが無限大になる点も含む全てのグラフが滑らかに繋がる点で接線が引けます。
----------------------------------------------------
また、Yを変数とした、グラフの、変数Yによる微分係数(dx/dY)は存在し、変数Yによっては微分可能ですが、それが微分可能であっても、変数xによる微分係数(dY/dx)が存在せず、変数xで微分不可能であることに変わりはありません。
(メモ知識)
以下の2つのグラフの関数は、いずれも、x→0の極限で、微分係数(dY/dX)が無限大に発散し、x=0では微分不可能です。

(メモおわり)
【右側微分係数と左側微分係数】
なお、
f(x) がx0 で微分可能でなくても、
h<0について、
または、
h>0について、
が存在することがあります.
下の図のような場合です。
その場合,
最初の値を左側微分係数(left-hand derivative ) と いい,
で表わし,
後の値を右側微分係数(right-hand derivative) といい,
で表わします.
微分可能の定義より,
が共に存在し,かつ両者が等しいとき に限りf(x) はx = x0 で微分可能となります。
------------(補足6)--------------------------
しかし、右側微分係数と左側微分係数が一致しなければ、その点では微分可能では無い(微分係数が存在しない)という微分可能の第1の定義には、以下のような違和感があります。すなわち、右側微分係数も左側微分係数も存在するのに、両者が一致しないからといって、その点を微分不可能と定義して良いのだろうか?と感じる違和感があるのです。
例えば、以下の図のグラフを考えてみます。
このグラフのx=0でのグラフの傾きは2つありますが、そのx=0での点で微分不可能と言うのは不適切だと考えます。なぜなら、そもそも、このグラフは、1つのxの値に対して2つのyの値を対応させている2価関数です。2つのyの値があるので、当然に2つの微分係数があります。その2つの微分係数がたまたま同じ値のyの点で現れたのがx=0の点であるというだけです。また、この2価関数を、xもyも、そして(x,y)の原点からの距離rを角度θの1価の関数と考えると、x=0での2つの傾き(dy/dx)は、θ=π/4の場合と、θ=-π/4の場合と、の2つの異なるθの場合における傾きと考えられます。そういう2つの微分係数が同じ(x,y)の点であらわれるからと言って微分不可能であると言う事はできません。
----補足6おわり----------------------
《関数の連続を前提にした、とある定理》
(とある定理)「ある点での関数の微分可能性を調べる場合に、
その点でその関数が連続である場合は、
微分係数の左側極限(真正の極限では無い)によっても左側微分係数を求めることができ、
微分係数の右側極限(真正の極限では無い)によっても右側微分係数を求めることができ、
微分係数の左側極限と微分係数の右側極限によって、微分可能性を調べることができる。」(とある定理おわり)
すなわち、左側微分係数を計算するのが面倒な場合:
x<x0 における微分係数が存在し、しかも関数f(x)がx0で連続な場合は:
と計算でき、x<x0 の微分係数の左側極限(真正の極限では無い)によって左側微分係数を求めることもできます。
右側微分係数についても:
x>x0 における微分係数が存在し、しかも関数f(x)がx0で連続な場合は:
と計算でき、x>x0 の微分係数の右側極限(真正の極限では無い)によって右側微分係数を求めることもできます。
ただし、関数f(x)がx0 で連続でない場合は、例えば下図のような場合は:
x=x0≡0 の左側微分係数は、-∞ですが、
x<0の関数f(x)のx<0における微分係数f’(x)は1であり、
x→0-
の極限でも、1になりますので、
x0が不連続点である場合に、上の「とある定理」を使うと(定理の適用違反ですが)、
x=x0≡0 の左側微分係数が1であるとしてしまい、
答えを間違えます。
このように、微分するには、先ず、その点で関数が連続であることを調べる確認作業を欠かしてはいけません。その確認の後に、この「とある定理」を使ってください。
(注意)
関数の変数xの値毎に、関数が微分可能か可能でないかが定義されています。
関数f(x)が変数xの値x0において微分可能の場合に、
関数f(x)が初等関数などの通常の関数の場合は、
Δyの誤差が以下の式であらわせます。
----ビッグオー O(Δx2)の 定義--------
ここで、O(Δx2)は、以下のように定義されます。
x=x0+Δxとする絶対値が十分小さいΔxに対して、
ある定数Mがあって、
|Δy-(df/dx)Δx| ≦ MΔxμ
が成り立つとき、
|Δy-(df/dx)Δx|はオーダーμの無限小であると言い、
Δy-(df/dx)Δx=O(Δxμ)とあらわす。
つまり、O(Δx2)は、MのΔx2倍程度の誤差をあらわす誤差関数です。(ΔX=0の場合は、O(0)=0と定義する)
Δxが0に近づくと、誤差O(Δx2)は、Δxよりも更に急速にMのΔx2倍のオーダー(概算値)で0に近づくということをあらわしています。
----(定義おわり)---------------
全ての関数について厳密に成り立つ関係としては:
関数f(x)が変数xのある値xにおいて微分可能であれば、Δxが小さくなればなる程、Δyの誤差が、MのΔx倍よりも急速に小さくなる誤差関数(スモールオー)で表した以下の式が成り立っています。
スモールオー o(Δx)の定義は、上の極限の式であらわされ、Δxよりも急速に小さくなる誤差関数です。(ΔX=0の場合は、o(0)=0と定義する)
Δxが小さくなればなる程、Δyの誤差o(Δx)が、MのΔx倍よりも急速に小さくなるので、Δxが十分小さいと考えれば、誤差が十分小さくなり、以下の近似式がいっそう正確に成り立つようになります。
そのため、Δyを上の式であらわして微分を計算して良いです。
【微分不可能が微分可能に変わる例】
(注意1)関数の変数を変換すると微分不可能な点が微分可能な点に変わることがある。
下図のグラフの関数は、O点では傾きが無限大なのでxで微分不可能です。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
この変数tで元の関数をあらわすと以下のグラフになります。
このグラフはO点で、tで微分可能です。
このように関数の変数を変換する、変数xでは微分不可能だった関数の点が、変数tでは微分可能になる、ということが起こり得ます。
という関係があります。
有限の微分係数が存在する(微分可能)という状態は、変数を変換すると変わることがあります。
それは、微分する変数に応じる「微分可能」という条件が、
いわば、
「式を0で割り算する計算をしてはいけない」
という計算の縛りと似た意味を持つことを意味しています。
(注意2)関数の変数を変換すると微分不可能な点が微分可能な点に変わることがあるもう1つの例を考える。
下図のグラフの関数は、O点では、左側微分係数と右側微分係数が異なるのでxで微分不可能です。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
この変数tで元の関数をあらわすと以下のグラフになります。
このグラフはO点で、tで微分可能です。
このように関数の変数を変換すると、変数xでは微分不可能だった関数の点が、変数tでは微分可能になる、ということが起こり得ます。
(注意3)関数の変数を変換すると、接する2つグラフが接さない2つのグラフに変換される例を考える。
下の2つの関数のグラフは、O点で同じ微分係数=0を持ち、O点で接しています。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
(この関数のグラフは、t=0の点での微分係数が無限大になってしまい、t=0では微分可能ではありません)
この変数tで元の2つの関数をあらわすと以下の2つのグラフになります。
元の2つのグラフの変数xを変数tに変換した2つのグラフは、O点で変数tで微分すると異なる微分係数を持ち、O点で接さず交差しています。
変数を変換すると、このように、互いに接する2つのグラフが、接触する点での微分係数が異なる2つのグラフに変わってしまうことがあることに気をつけましょう。
すなわち、「2つの接するグラフが接点において等しい微分係数を持つ」ことが、グラフの座標変換によって変わってしまい2つのグラフの接触点での微分係数が等しく無くなることが有り得ます。
その様なおかしな事が起こる場合は、変数のその値で微分可能では無い関数を使って変数を変換すると生じ得ます。おかしな事が起こらないようにする1つの十分条件として、変数変換に使う関数を、変数のその値で「微分可能」な関数を使えば、変数がその値の部分でのグラフにはおかしな事が起こりません。
「微分可能」は、このようにおかしな事が起こらないようにする十分条件なのです。これが、「微分可能」と「微分不可能」を区別する意味だと考えます。
この「微分可能」によって、自然な直感で想像できる事がどのようにして生じ得るかの答えは、「合成関数の微分の公式」によって明らかにされますので、それまで地道に勉強を進めて欲しいと思います。
(交差している2つのグラフが、変数変換すると互いに接する2つのグラフに変わる例)
上図のように、変数tの関数f(t)とg(t)との2つの関数値をY=f(t)、及びY=g(t)とする。
f(t)=t
g(t)=t/2
とする。 この場合に、上図のように、2つのグラフが、tY座標平面上では互いに交差しているだけで、接していない。
このグラフの変数tを以下のグラフの関数であらわす媒介変数xを考える。
変数tをこのグラフの関数であらわす媒介変数Xを使うと、
XY平面上で先の2つのグラフをあらわすと以下の図の様になる。
x≧0の場合に:
関数f(t)=x2
関数g(t)=x2/2
になる。
この様にXY座標平面上では、互いに接する2つのグラフに変換されてしまった。
すなわち、接さずに単に交差しているだけの2つのグラフが、互い接するグラフに変わってしまった。
(行なって良い変数変換の条件)
tY座標平面上の2つのグラフがある変数値において接するか否かを調べている時に、そのように変わってしまわないようにするための、行なって良い変数tの媒介変数xへの変数変換は、その2つのグラフが交差する点の位置の変数値において:
(A)
dt/dx ≠ 0
となることが必要です。
(B)
また、その関数が”微分可能”であることも必要で、すなわち、その2つのグラフが交差する点の位置の変数値において:
dt/dx ≠ ±∞
も必要です。
なお、変数を変換する関数t=m(x)が、
dm(x)/dx≠0となるxの連結区間では、
m(x)は単調増加関数か単調減少関数になります。
その区間の単調増加か単調減少な関数t=m(x)には逆関数x=p(t)が存在します。
特に、
dt/dx ≠ 0,
dt/dx ≠ ±∞,
が成り立つ場合には、
逆関数の微分の公式も成り立ちます。
この2つの条件を満足する関数t=m(x)で変数変換をするならば、グラフの所定の点での「微分可能」または「微分不可能」というグラフの性質が変数変換の後でも同じに維持されます。
例えば、t=m(x)=log(x)という関数は、X=0以外の点では、この2つの条件を満足します。
そのため、この関数t=m(x)を使って変数変換するならば、X=0以外の点では、「微分可能」と「微分不可能」という性質が変わりません。
(行なって良い変数変換の使用例)
以下の式1であらわされるグラフを考えます。
Y=xa (式1) (定数 a は所定の実数)
この式1であらわされるグラフは、
グラフが滑らかである大部分の変数値xにおいて、
傾きが∞にならない点で、微分可能です。
この式1のグラフの微分可能性は、以下の様に変数変換して調べることもできます。
この式1を関数log(x)で変換すると、
log(Y)=a*log(X) (式2)
に変換されます。
この式2を
Z=log(Y) (Z>0)
t=log(X) (t>0)
で変数変換すると、
Z=a*t (式3) (ただし、Z>0,t>0)
が得られます。
この式3であらわされるグラフは、元の変数であらわされたグラフと、「微分可能」と「微分不可能」という性質が変わりません。
式3のグラフは「微分可能」ですので、元の式1であらわされたグラフも「微分可能」であることがわかります。
(行なって良い変数変換に関する注意)
「微分可能性」の性質を維持する変数変換の条件は、以上で説明した通りですが、その条件を満足していなくても、式を自由に関数で変換して、関数の微分係数の計算式を導きだして良いのです。0を0で割り算するような計算ルールに違反するような計算をせず正しく微分係数の計算式を導き出せれば、その計算式が得られたことが、その関数が「微分可能」であることの証明になります。
ただし、上の条件を満足せずに、微分係数の計算式を導き出せた場合でも、以下の場合には「微分可能」にはなりませんので注意が必要です。
(1)関数f(x)が、x≧x0 と、x<x0 とで異なる式で定義されていて、x<x0 でのf’(x)の、x→x0 における値と、x>x0 でのf’(x)の、x→x0 における値が異なる場合、変数xの範囲のx0 ーδ<x <x0 +δ の範囲における微分係数の値が1つに確定しないので、x0 で微分不可能です。
(2)このように、微分可能性を、微分係数の計算式の存在によって判定しようとする場合には、変数xの範囲のx0 ーδ<x <x0 +δ において全ての関数値f(x)をしらべることができるか否かをチェックして判定するよう注意してください。
例題2.4
f(x) = xn (n 整数) を微分してみましょう.
となります。
(解答おわり)
が得られました。
次に、以下の微分も計算してみます。
この図形を直線y=xに関して折り返して考えます。
こうして、
が得られました。
(微分の式の前提条件:関数が存在すること)
微分をあらわす式:
(dy/dx)は関数f(x)の導関数をあらわす式です。
そのため、
(dy/dx)=(df(x)/dx)
であり、変数yを微分で使う場合には、
y=f(x)とあらわす関数f(x)が必ず存在することが、変数yを使う前提条件にあります。
関数f(x)が必ず存在するということは、変数xに対して、必ず1つの値のy=f(x)が定まる関係(規則)が、変わらず、存在するということです。
(関数が存在しない例)
以下の関数f(x)で:
(df(x)/dx)=0となっているグラフの部分(y=0の部分)については、以下の逆関数g(y)のグラフの様に:
y=0となっているグラフの部分では、逆関数g(y)が存在しない。 そして、g(y)のy=0での右側極限と左側極限が一致しない。そのため、Δy→0の場合にΔx→0とはならない。
----関数が存在しない例おわり------------------
微分の式は、定まった関数であらわされる関係が必ず存在する変数yとxその他の媒介変数の間の関係をあらわす式です。
微分の計算で使う全ての変数yやxやその他の媒介変数同士は、必ず、その変数を他の変数であらわす不変な関数で結ばれていることが前提にあります。
その関数はどの式であっても良いですが、計算の途中で変化することが無い、いつも変わらない関係式であることが微分の計算の前提になっています。
(微分可能な関数を選んで微分すること)
下図のグラフの関数はでこぼこしていて、でこぼこがあらゆる細部にまで在り、どの有理数のxの位置においても微分不可能な関数の例です。
また、微分不可能な関数F(x)として、連続関数であり、かつ、あらゆるところで微分不可能な関数であるワイエルシュトラス関数F(x)などもあります。
この図の関数のように、関数が微分不可能な変数の値を判定して、変数の範囲(定義域)から除外するために、「微分」の定義を使って関数の変数を選別して、その変数の範囲の関数を微分計算の対象にします。
実際は、微分不可能な関数は、警戒しなければならないほどに多く存在するわけでは無く。数学で学んで来た、ほとんど大部分の初等関数は微分可能な関数です。
また、上のグラフのようf(x)が微分不可能な変数の値(有理数)が無限にある関数f(x)であっても、積分はできます。
(ただし、あらゆるところで微分不可能な関数F(x)については、その関数F(x)を微分した結果の片りんさえも存在しないので、その関数F(x)は何かの関数f(x)の積分では得られません。)
元の関数f(x)が連続関数等の、関数の極限が存在する関数の場合は、その関数f(x)を積分して得た関数F(x)は微分可能な関数になります。こうして、極限が存在する関数f(x)の集合の要素の各関数f(x)を積分して関数F(x)の集合を作れば、その関数の集合の要素の各関数F(x)は、どれも微分可能な関数であることが保証されます。
(「リーマン積分可能」の定義)
「微分積分学入門」(横田 壽)の124ページから125ページに「リーマン積分可能」の定義が書いてあります:
(この本は書店で購入できます。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
ここではドイツの数学者G.F.B. Riemann (1826-1917) によって示されたRiemann 積分につ いて学んでいきます.リーマン積分による「積分可能」の定義は、全ての種類の「積分可能」の定義の基礎になっています。
f(x) は閉区間[a, b] で定義されているとします.この閉区間[a, b] を次のような点xi(i = 1, 2, . . . , n) でn 個の小区間に分割します.
(a = x0 < x1 < x2 < · · · < xi < · · · < xn = b)
この分割をΔ で表わし, Δxi = xi − xi−1 (i = 1, 2, . . . , n) のうちで最も大きい値を|Δ| で 表わします.
いま,それぞれの小区間[xi−1, xi] のなかに任意の点ξi をとり,Riemann 和 (Riemann sum) とよばれる次の和を考えます.
このとき、
となる実数S が存在するならば,このS をf(x) の定積分(definite integral) といい, f(x) は閉区間[a, b] で積分可能(integrable) であるといいます.また,このS を次のように表わします.
つまり関数f(x) が閉区間[a, b] で積分可能であるということは,分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まるということです.
この定義に従い、関数の積分可能性を以下の様にして調べることができます。
先ず小さな閉区間[a, b] を定めて、
その区間の小区間への分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まる(積分可能)か否かを調べることができます。
【積分が不可能な関数】
下のグラフの関数f(x)のように、どの位置においても関数の極限が存在しない関数もあり得ます。
例えば、
xが有理数の場合にf(x)=0であって、
xが無理数の場合のf(x)=1
という、極限が存在しない関数f(x)などです。
そういう、極限が存在しない関数f(x)を積分して関数F(x)を得た場合(もし積分できた場合)、その積分により得られた関数F(x)は微分可能だろうか。
そもそも、微分の計算は極限を求める計算なので、その関数f(x)が積分できても、その積分した関数F(x)を微分した場合に、元の関数f(x)は(極限値が存在しないので)、微分によっては得られないと考えます。
この関数f(x)の変数x=x1からx=x2までの変数xの閉区間をn等分した小区間を作り、その各小区間毎にf(x)の値f(ξ)を求めて、その値の和で積分します。
(1)その際に、 変数x=ξが全て有理数なら、f(ξ)=0になり、積分結果は0になります。
(2)一方、変数x=ξが全て無理数√2の有理数倍なら、f(ξ)=1になり、積分結果は(x2-x1)になります。
(3)小区間内の変数xの点ξの選び方によってf(ξ)の和による積分結果が変わるような計算の値は定かでは無いので、その様な関数f(x)は積分することができません。
なお、以下の関数F(x)は微分可能ですが、それを微分して得た導関数f(x)に不連続点(微分不可能な点)があります。
x≠0の場合:
x=0の場合: F(0)=0,
この関数F(x)はx≠0の場合に微分可能で、
その導関数f(x)は:
になり、xが0に近づくとー1と1の間を振動します。
この導関数が含むcos(1/x)の関数が以下のグラフであらわす形の関数になるからです。
X=0の場合にも、F(x)は微分可能で:
というように、0になります。
そのため、関数F(x)は、全てのxの値で微分可能です。
しかし、関数F(x)の導関数f(x)は、x=0で値f(0)=0を持ちますが、x=0で不連続です。
このF(x)のように、微分すると不連続点を持つ関数f(x)になるが、F(x)自体は、全ての変数値で微分が可能という関数F(x)があるのです。
なお、関数f(x)が変数xのある値で不連続ならば、必ずその点でf(x)は微分不可能になります。これは、「関数が変数xのある値で微分可能ならば、必ずその点で連続である」と言う定理の対偶として成り立っています。
このように、微分積分学では、あらゆる関数に微分積分を行う理論を作ろうとすると、いろいろな難しい問題があることがわかりました。
微分積分学で、難しい問題が生じない関数の範囲を把握して、その範囲内で微分積分の計算をすることで、応用上で微分積分を使い易くできます。
そのため、使い易い関数として、極限が存在し、かつ、変数xの実数のすき間がない1つながりの区間内で連続な「連続関数」 を主に扱う対象にする。また、「微分可能性」で関数の変数の定義域を微分可能な区間に制限する。そのように、扱う関数を制限します。その関数の変数xの区間内で、その関数に関して成り立つ法則を把握して、種々の公式を導き出して使う。そうすることで微分積分学を最大限に応用できるようになります。
(連続関数を使う利点)
変数xが、閉区間の、
a≦x≦b
で連続な連続関数f(x)の関数については、
(関数の連続性については連続性の定義が拡張されている) で説明したように、閉区間の端点での連続性の定義の修正があります。
また、大学生以上で、閉区間での端点での微分可能の定義を修正することで、
関数f(x)が連続な変数xの範囲で、関数f(x)が微分可能にもなり得るという、微分の概念が使い易くされています。
-----(補足7)----------------
なお、この様に定義の修正をした微分可能の概念を使った定理を証明する場合、少なくとも微分の定義については、その定義の修正も検討して定理を証明する煩わしさを避けるため、微分可能な領域を開区間に限定して、各定理を定義しています。
平均値の定理の記述などで、
「関数が閉区間a≦x≦bで連続であって、開区間a<x<bで微分可能である場合に」
という条件を定めているのは、閉区間の端点での微分可能の定義の修正を考えて定理を証明する煩わしさを避けるため、定理の前提条件をその様に、閉区間で連続で開区間で微分可能と定めています。
--------補足7おわり---------------
こうして、微分積分学は、微分可能な関数と積分可能な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をします。「微分可能」と「積分可能」という制限条件を定め、その制限条件を満足する関数を扱うのが微分積分学だと認識することがとても大切です。
その様に、「微分可能」の制限条件を定めて、その「制限条件」を外れた関数については”考えないこと”にするのが、「微分可能」を定義した本当の理由だと思います。
《下図に各種の関数の集合の包含関係をまとめた》
積分前の関数f(x)と、微分前の関数F(x)との、変数xの一部の定義域での微分積分のあり得る関係が以下の図であらわせます。
(上図で、関数f2(x)は、除去可能な不連続点を除去した関数です。関数F(x)は、関数F(x)の不連続点を除いた変数xの範囲でf(x)の不定積分であるとともに、f2(x)の不定積分でもあります)
「微分可能」な関数と「積分可能」な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をすることが微分積分学の本質です。しかし、その本質を考える礎である一番大切な概念である「微分可能」と「積分可能」を高校2年には教えない。高校3年に至っても「積分可能」の概念を教えていないようです。
しかも、1997年からは、日本の高校の数学IIで面積が無定義に用いられという、数学センスを否定する蛮行が行なわれた。そして、関数f(x)のグラフとx軸で囲まれる領域の面積を,x方向で微分するともとの関数f(x)になり、面積の微分がf(x)となるという本末転倒なことを教えるようになった。
現在の高等学校の教科書は,積分の概念の説明を回避している。
このようなデタラメな教育では、高校生に微分積分が分からないのも無理無いと考えます。
(微分積分の教育方針)
ヨーロッパやアメリカでは、「高校で微分積分を教えるのは、直感にうったえる内容に限られ、正確な微分積分を教えられない」という理由で、微分積分は大学生に教える科目になっています。
日本の大学でも、その欧米の教育に合わせて、初めて学ぶ者に分かるように微分積分を改めて教育しているようです。
大学で使う微分積分の参考書は、高校で教える微分積分の知識を全く知らない学生に理解できるように書かれています。
しかも、大学生向けの微分積分の参考書の方が、日本の高校生向けの微分積分の参考書よりやさしく分かり易い。
高校の微分積分を勉強するなら、先ず、大学生向けの微分積分の参考書を読むことを推薦します。高校の微分・積分の教科書は分かりにくいだけで無く、間違いも含まれています。読まない方が良いのではないかと考えます。
大学生向けの参考書の、
「微分積分学入門」(横田 壽)
を読んでみることをお勧めします。
(この本は書店で購入できます。)
(しかし、同じ著者の書いた高校生向けの参考書「確実に身につく微分積分(2012年)」の1版は、内容が劣化しているのでお勧めできません。大学生向けの本物の知識の参考書「微分積分学入門(2004年)」を読んでください。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
「微分積分学入門」(横田 壽)の読み方は、 66ページから始まる2章「微分法」の以前のページは斜め読みして、何が書いてあるらしいかを漠然と把握しておいて、2章「微分法」以降を精読することをお勧めします。読んでいるうちに知らない関数や概念が出てきたら、66ページ以前に書いてありますので、探して、その部分を読んで理解するように勉強してください。
リンク:
高校数学の目次





















































