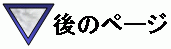(微分積分学の基本定理の正しい定義の開始)
関数y=f(x)が、
a≦x≦b
上で連続とする。
その条件が成り立つならば、必ず、
という計算をすることができる。
そして、次のことが成り立つ。
(1)不定積分S(x)はf(x)の原始関数の1つである。
(原始関数は連結区間で1つながりに連続な関数であって全ての点で微分可能な関数)
(2)F(x)をf(x)の任意の原始関数とすると、
が成立する。
(定理の定義おわり)
すなわち、基本定理の意味は、その定理の命題が、S(x)の式の積分計算を可能にする十分条件(関数が連続である)を述べたものであることがわかります。
この基本定理の命題が正しいか否かは、連続関数(その領域内で関数が連続)が、「関数の積分を可能にする十分条件」になるか否かによって決まる、そして、関数はその関数が連続な領域で積分可能なので、微分積分学の基本定理が成り立つ、ということがわかります。
(まぼろしの基本定理の予感)
微分積分学の基本定理をこの形で表現すると、微分積分学の基本定理の抱える問題点が良く分かると思います。
連続関数(その領域内で関数が連続)については、積分して微分すると元の関数が得られるという便利な特徴がありますが、他の関数にも、そういう特徴を持つ関数が無いか、調べてみましょう。
下図の関数F(x)とF’(x)=f(x)を考えてみます。
関数F(x)はx=0で連続な関数です。
この関数F(x)を微分すると、下図の関数f(x)が得られます。
この関数f(x)はx=0では連続ではありません。
しかし、この関数f(x)を積分すると、F(x)を得ることができます。
この関数f(x)はx=0で連続で無いので、x=0を含むxの範囲で微分積分学の基本定理が適用できません。
しかし、
x=0を含む範囲で、微分積分学の基本定理の結論である:
が成立します。
このことから、
以下のまぼろしの基本定理がありそうです。
【まぼろしの基本定理】
関数y=F(x)が、
a≦x≦b
上で連続とする。
関数F(x)が、
a<x<b
で微分可能で、その範囲内で、
F’(x)=f(x)になるとする。
ここで、関数f(x)の値が存在しない境界点のx=a又はbがある場合:
関数f(x)の値が存在するxの値の範囲がa<x<bならば、そのxの値の範囲の境界点の極限値のaとbが考えられる。
その関数f(x)の値が存在するxの値の範囲a<x<bの範囲内で関数f(x)を積分した結果のF(x)の値の、
x→a の極限を、F(a)とし、
x→b の極限を、F(b)とし、
a<x<bでの積分範囲の極限の、a≦x≦b
での積分を、
F(b)-F(a)
と定義する。そう定義すると:
が成立する。
(まぼろしの基本定理の定義のおわり)
このまぼろしの基本定理は、数学者の藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」に、以下の通りに書いてありました。
不連続関数f(x)の積分を広義積分と呼び、
その積分において、関数f(x)の積分範囲
a≦x≦b
内で連続な不定積分(その積分範囲内に微分不可能な点があっても良い)F(x)が得られたら、
(1)それは、不連続関数f(x)が積分可能である証拠であり、
(2)以下の計算で定積分を計算して良い事が書いてあります。
F(b)-F(a)
よって、
不連続な関数f(x)に対して、
その積分区間で連続な不定積分F(x)が見つかったなら、
その不定積分F(x)を使って定積分を計算して良いです。
(しかもそのF(x)はその積分区間内で微分不可能な点があっても良い)
また、小寺平治・著「はじめての微分積分15講」(2,200円)の103ページにも、このことが書いてあります。
「やさしく学べる微分積分」(石村園子)の106ページの形の微分積分学の基本定理を使うと、以下の定理がすぐに導き出せる。
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数f(x)がある場合、
a<x<b
の範囲で、
F’(x)≡f(x)>0
ならば、
a≦x≦bの範囲で、
f(x)の原始関数F(x)は単調増加である。
(定理の定義おわり)
(証明開始)
関数f(x)が
a≦x≦b
で連続であるので、
a≦x1<x2≦b
なるx1とx2に関して、
微分積分学の基本定理により、
よって、
F(x)は単調増加である。
(証明おわり)
高校で扱う連続関数(その領域内で関数が連続)はこの定理の条件を満足するので、この定理があれば十分と思いますが、
藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」に書いてあったまぼろしの基本定理:
被積分関数f(x)が連続関数(その領域内で関数が連続)で無くても、
その様に不連続な関数f(x)に対して、
その積分区間で連続な不定積分F(x)が見つかったなら、
その不定積分F(x)を使って以下の計算で定積分を計算して良い。
F(b)-F(a)
が使えます。
実際、以下の定理があります。
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)がある場合、
a<x<b
の範囲で、
F’(x)≡f(x)>0
ならば、
a≦x≦bの範囲で、
関数F(x)は単調増加である。
(定理の定義おわり)
この定理の証明に、「まぼろしの定理」を使えますが、先ずは、それを使わずに、伝統的に確立されている平均値の定理を使って、この定理を証明しておきます。
(証明開始)
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)が:
a<x<b
の範囲で微分可能で、
F’(x)=f(x)
の場合、
平均値の定理によって、
a≦x1<x2≦b
なるx1とx2に関して、
(F(x2)-F(x1))/(x2-x1)=f(x)
となるxが、
a≦x1<x<x2≦b
に、少なくとも1つ存在する。
その範囲で、
f(x)>0
なので、
F(x2)>F(x1)
である。
よって、F(x)は単調増加である。
(証明おわり)
このように証明できるこの定理は、まぼろしの基本定理を支える基礎の1つになっていると考えても良いと思います。
(備考2)
なお、全ての種類の関数における、積分前の関数f(x)と、微分前の関数F(x)との、変数xの一部の定義域での微分積分のあり得る関係が以下の図であらわせます。
(なお、F(x)として考えられる関数の、関数が連続な領域内の至るところ微分不可能な関数であるワイエルシュトラス関数等は、不連続点を持たないが、微分不可能です。)
(上図で、関数f2(x)は、除去可能な不連続点を除去した関数です。関数F(x)は、関数F(x)の不連続点を除いた変数xの範囲でf(x)の不定積分であるとともに、f2(x)の不定積分でもあります)
上図の、f(x3)とF(x3)の関数のセットの例:
以下で定義する関数のセットでは、f(x)にx=x3で除去不可能な不連続点があって、f(x)は不連続関数(その点で関数が不連続な関数であって、その点以外の領域では関数が連続な連続関数である)です。
しかし、この不連続点を持つ関数f(x)を、その不連続点を含む範囲で定積分することで定義した関数F(x)が、その不連続点の位置x3でも変数xで微分可能で、F(x)を微分すると再び不連続点を持つf(x)が得られます。
(F(x)の定義)
x≠0の場合:
x=0の場合: F(0)=0,
(導関数f(x))
この関数F(x)はx≠0の場合も、x=0の場合も、微分可能で、
その導関数f(x)は、以下の式であらわせます。
x≠0の場合の微分:
になり、xが0に近づくとー1と1の間を振動します。
この導関数が含むcos(1/x)の関数が以下のグラフであらわす形の関数になるからです。
X=0の場合にも、F(x)は微分可能で:
というように、0になります。
そのため、この導関数f(x)は、x=0で連続ではありませんが、F(x)を微分することで得られます。
この導関数f(x)は積分可能であり、積分するとF(x)になります。
この関数F(x)はx=0で連続な連続関数(その点で関数が連続)です。
F’(x)=f(x)はx=0で微分可能では無く不連続なので、x=0を含むxの範囲では微分積分学の基本定理が適用できませんが、「まぼろしの定理」が適用できるように思います。
この様な複雑な関係の中から、比較的に扱い易い連続関数(その領域内で関数が連続)を使って従来の微分積分学の基本定理が定められています。
また、大学以上の微分積分学では、積分の定義をどんどん拡張して、何でも積分できるようにして、ある関数f(x)を積分して不連続点を持つ関数F(x)を得ることができるようにし、その不連続点を持つ関数F(x)を微分して関数f(x)を得ることができるように、微分の定義も拡張するというような事も行なわれます。
そのように微分・積分の定義を拡張する入口に、微分積分の基本定理が置かれています。
そのため、微分積分学の基本定理の:
という式の意味することは:
この公式の前提条件以外の条件によってこの式と異なる結果が得られるわけでは無く、
この式を成り立たせるように、f(x)とF(x)を対応させる規則である微分と積分とを矛盾が生じ無い様に定義を修正して、この式を成り立たせているのです。
そういうわけなので、
a≦x≦bの範囲で、
F(x)が連続な関数とし、
そのF(x)が、
a<x<bの範囲で微分可能で、
f(x)=F’(x)
が有限な値で存在する場合は、
f(x)の積分の範囲の取り方を、
f(x)が、x=aやx=bで存在しない場合にも、
f(x)をaからbの範囲で積分可能にするように積分の定義を微妙に修正するだけで、
という式を計算可能にする「まぼろしの定理」を作りあげることができます。
そういう、積分の定義の修正を加えるだけで、「まぼろしの定理」が適用可能になります。
「やさしく学べる微分積分」(石村園子)の107ページの説明にある、106ページの形の微分積分学の基本定理への感想:「この定理は、f(x)の原始関数を定積分を使って定めてあるところがすばらしい」と書いてあるとおり、
素晴らしい表現だと思います。
という形の定積分を使ってf(x)原始関数F(x)を定めている本質的な表現をしているので、微分積分学の基本定理の前提である:
連結区間a≦x≦b
で関数f(x)が連続であれば:
という条件は、定積分を可能にしている条件に過ぎないことが顕わに見えています。
【まぼろしの基本定理の厳密な定義】
定積分の定義が修正されて、従来の積分の定義では不定積分F(x)が定義できなかった関数f(x)を、同じ形の定積分で不定積分F(x)を定義できるように積分の定義を修正すれば、微分積分学の基本定理が適用できる関数f(x)の種類を拡大して「まぼろしの基本定理」を構成できることが分かります。
(1)そして、そのように積分の定義を修正し、F(x)が連続関数(その領域内で関数が連続)であるという条件だけを定め、
f(x)が連続関数(その領域内で関数が連続)で無くても(積分範囲内にf(x)の関数値が存在しない不連続点があっても)積分を適用できるようにする。
(2)更に、 微分する点を含む領域内で連続な関数F(X)の微分により得ることができる関数f(x)を、以下の処理で定義することができます。
(2-1)すなわち、ある関数f(x)の不連続点x=x0で関数が極限値を持つ場合、その不連続点での関数f(x0)の値をその極限値に修正して不連続点を解消する。
(2-2)その他の不連続点については、その不連続点x=x0 を含む領域で関数f(x)を積分して関数F(x)を得て、関数F(x)を微分した場合の不連続点x=x0で導関数の値が元のf(x0)と異なる場合(例えばF(x)がx0で微分不可能で関数値が無い場合)には、関数f(x)の関数値f(x0)を、その導関数の値に修正する。
(2-3)以上の処理で定義した関数f(x)を、「まぼろしの基本定理」を適用する対象の関数f(x)とします。すなわち、定理の対象にする関数f(x)を、連続関数F(x)を微分することで得られる関数に限定します。
また、定理の対象にする連続関数F(x)も、それを微分した関数を積分することで再び得られる関数に限定します。詳しくは、連続関数F(x)を、それが微分不可能な点が散在するにしても、大部分のxの値で微分可能な連続関数F(x)に限定します。
そのように限定した関数f(x)に対して、その修正した定義による積分の計算をすると:
が成り立ち、また、次のことが成り立つ。
(3)S(x)はf(x)の不定積分である。
S(x)は連続関数(変数xの連結区間内で関数が1つながりに連続)になる。
(4)連続関数F(x)をf(x)の任意の不定積分とすると、
が成立する。
(まぼろしの基本定理の定義おわり)
このまぼろしの基本定理が 成り立つ条件を整えるために、f(x)を積分した結果の(xの連結区間内で)連続な関数F(x)を微分した導関数の関数値がf(x)の関数値と同じになるという特徴がある関数f(x)を選びました。(そうならない関数もありますが、そういう関数f(x)は除外してあります)
この「まぼろしの基本定理」を使えば:
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)がある場合:
a<x<b
の範囲で、
F’(x)≡f(x)>0
ならば、
a≦x≦bの範囲で、
関数F(x)は単調増加である。
(定理の定義おわり)
という定理を、微分積分学の基本定理を使った証明の場合と同様な手順に従って、まぼろしの基本定理を使って証明することができます。
ただし、この様に定義した関数f(x)に対して、このように修正した積分方法で積分することで得られる連続関数F(x)に限定された証明にはなります。例えば、関数が連続な領域のあらゆるところで微分不可能な関数であるワイエルシュトラス関数等は連続関数F(x)の候補として使えませんが、、、(例え候補になれても、微分が不可能なので、その関数はこの定理のF(x)の条件から外れる)。
こうして、この定理が対象にする連続関数(所定領域内で連続な関数)F(x)が、その様に定義された関数f(x)から積分することで得られる連続関数F(x)に限定されます。そして、関数が連続な領域の至るところ微分不可能な関数等が定理の対象とする連続関数F(x)から除外されます。そういうふうに、まぼろしの基本定理が対象にできる連続関数F(x)が制限されている、定理の限界によって、この証明方法で証明されるのは、そういう連続関数F(x)に係る場合だけに限定されるので、この証明方法は、全ての連続関数F(x)について定理を証明したわけでは無く、この証明は不完全です。
しかし、これにより、この定理の確からしさを確認でき、この証明方法によって定理の持つ意味が分かると考えますので、この証明方法の価値があると考えます。
また、F’(x)がa<x<bで微分可能であるという条件があるので、その条件が加わった連続関数F(x)は、まぼろしの基本定理の対象にする連続関数の集合に含まれることを証明できそうだと考えます。それが証明できれば、以上の証明方法は、「完全な証明」になり得ると考えます。
なお、この定理の対偶も正しく成り立ちますが、その対偶の一部の、正しく成り立つ定理を、以下の様に表現することができます。
【定理の対偶(の一部)】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)であり、
a<x<b
の範囲で微分可能な関数F(x)が、
a≦x≦bの範囲で、単調増加で無い
(例えばある領域でF(x)が同じ値に停留したり、減少したりする)
ならば、
a<x<b
の範囲内に、
F’(x)≡f(x)≦0
となる点が必ず存在する。
(定理の定義おわり)
(注意)先の定理(命題)の対偶は、以下の様に、定理の前提条件(関数F(x)が所定領域内で連続であること等)を否定した場合も想定した命題になります。
【定理の対偶】
a≦x≦bの範囲で、
関数F(x)が単調増加で無い
(例えばある領域でF(x)が同じ値に停留したり、減少したりする)
ならば、
(場合1)
a≦x≦b
の範囲で、関数F(x)が連続で無いか、
(場合2)
関数F(x)はその範囲で連続ではあるが、
a<x<b
の範囲で微分不可能な点があるか、
(場合3)
関数F(x)はその範囲で連続で、
かつ、 a<x<b の範囲で微分可能
ではあるが、
a<x<b の範囲内に、
F’(x)≡f(x)≦0
となる点が必ず存在する。
かの何れかである。
(定理の定義おわり)
先の【対偶の一部】は、この【対偶】における場合3を述べた命題でした。
ここで、条件付きで定義した命題は、
その条件が成立しないときには、その命題の結論が成立しない事もあるという意味を含んだ命題になりますので、
結局、上の場合1と場合2の想定は、条件付きで定義した命題の意味の中に含まれていることになります。
そのため、先の、【定理の対偶(の一部)】の命題は、
結局、定理の対偶によって表現される内容の全部を含んでいます。そのため、定理の対偶の一部では無く、定理の対偶の全体をあらわすものでした。
定理の成立条件の位置付けをこの様に解釈すると、この「定理の対偶」の定理(命題)の対偶が、以下の様にあらわせます。
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続で、
a<x<b
の範囲で微分可能な関数F(x)が、
その範囲での微分係数が全て、
F’(x)≡f(x)>0
ならば、
その関数F(x)は、a≦x≦bの範囲で、単調増加である。
(定理の定義おわり)
この命題は、元の定理ですので、元の定理が「対偶の対偶」によって再現できました。
なお、
「まぼろしの定理」 を使えば、単調増加関数F(x)の範囲を拡張した以下の定理もやさしく証明できます。
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)がある場合:
a<x<b
の範囲で、
F’(x)≡f(x)≧0
であり、
そのうち、
f(x)=0となる点は有限個数存在するだけならば、
a≦x≦bの範囲で、
関数F(x)は単調増加である。
(定理の定義おわり)
という定理も簡単に証明できます。
積分範囲内に、F’(x0)=0となる点
x=x0が、
a≦x≦b内の、
c<d
となるcからdまでの領域内の全ての点でF’(x)=0であれば、
そのcからdまでの積分結果=0
となります。
しかし、有限の幅を持った領域にわたっては
F’(x)=0
とはならず、
所定領域内に、
F’(x)=0となる点が有限の個数有るだけならば、
その領域での積分結果>0
になるからです。
もう1つ、以下の関数F(x)が単調増加であることも、
「まぼろしの定理」を使ってやさしく証明できます。
(関数F(x)の定義)
x=0のとき: F(x)=0,
0<x≦1において、
F’(x)=1+cos(1/x),
この関数F(x)は、
0≦x≦1
の範囲内に、 無限個のF’(x)=0となる点がありますが、
0≦x≦1
の範囲内で連続、かつ、単調増加です。
このことは、
「まぼろしの定理」を使ってF’(x)を積分してF(x)を求める計算式を書けば分かります。
リンク:
高校数学の目次
a≦x≦b
上で連続とする。
その条件が成り立つならば、必ず、
という計算をすることができる。
そして、次のことが成り立つ。
(1)不定積分S(x)はf(x)の原始関数の1つである。
(原始関数は連結区間で1つながりに連続な関数であって全ての点で微分可能な関数)
(2)F(x)をf(x)の任意の原始関数とすると、
が成立する。
(定理の定義おわり)
すなわち、基本定理の意味は、その定理の命題が、S(x)の式の積分計算を可能にする十分条件(関数が連続である)を述べたものであることがわかります。
この基本定理の命題が正しいか否かは、連続関数(その領域内で関数が連続)が、「関数の積分を可能にする十分条件」になるか否かによって決まる、そして、関数はその関数が連続な領域で積分可能なので、微分積分学の基本定理が成り立つ、ということがわかります。
(まぼろしの基本定理の予感)
微分積分学の基本定理をこの形で表現すると、微分積分学の基本定理の抱える問題点が良く分かると思います。
連続関数(その領域内で関数が連続)については、積分して微分すると元の関数が得られるという便利な特徴がありますが、他の関数にも、そういう特徴を持つ関数が無いか、調べてみましょう。
下図の関数F(x)とF’(x)=f(x)を考えてみます。
関数F(x)はx=0で連続な関数です。
この関数F(x)を微分すると、下図の関数f(x)が得られます。
この関数f(x)はx=0では連続ではありません。
しかし、この関数f(x)を積分すると、F(x)を得ることができます。
この関数f(x)はx=0で連続で無いので、x=0を含むxの範囲で微分積分学の基本定理が適用できません。
しかし、
x=0を含む範囲で、微分積分学の基本定理の結論である:
が成立します。
このことから、
以下のまぼろしの基本定理がありそうです。
【まぼろしの基本定理】
関数y=F(x)が、
a≦x≦b
上で連続とする。
関数F(x)が、
a<x<b
で微分可能で、その範囲内で、
F’(x)=f(x)になるとする。
ここで、関数f(x)の値が存在しない境界点のx=a又はbがある場合:
関数f(x)の値が存在するxの値の範囲がa<x<bならば、そのxの値の範囲の境界点の極限値のaとbが考えられる。
その関数f(x)の値が存在するxの値の範囲a<x<bの範囲内で関数f(x)を積分した結果のF(x)の値の、
x→a の極限を、F(a)とし、
x→b の極限を、F(b)とし、
a<x<bでの積分範囲の極限の、a≦x≦b
での積分を、
F(b)-F(a)
と定義する。そう定義すると:
が成立する。
(まぼろしの基本定理の定義のおわり)
このまぼろしの基本定理は、数学者の藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」に、以下の通りに書いてありました。
不連続関数f(x)の積分を広義積分と呼び、
その積分において、関数f(x)の積分範囲
a≦x≦b
内で連続な不定積分(その積分範囲内に微分不可能な点があっても良い)F(x)が得られたら、
(1)それは、不連続関数f(x)が積分可能である証拠であり、
(2)以下の計算で定積分を計算して良い事が書いてあります。
F(b)-F(a)
よって、
不連続な関数f(x)に対して、
その積分区間で連続な不定積分F(x)が見つかったなら、
その不定積分F(x)を使って定積分を計算して良いです。
(しかもそのF(x)はその積分区間内で微分不可能な点があっても良い)
また、小寺平治・著「はじめての微分積分15講」(2,200円)の103ページにも、このことが書いてあります。
「やさしく学べる微分積分」(石村園子)の106ページの形の微分積分学の基本定理を使うと、以下の定理がすぐに導き出せる。
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数f(x)がある場合、
a<x<b
の範囲で、
F’(x)≡f(x)>0
ならば、
a≦x≦bの範囲で、
f(x)の原始関数F(x)は単調増加である。
(定理の定義おわり)
(証明開始)
関数f(x)が
a≦x≦b
で連続であるので、
a≦x1<x2≦b
なるx1とx2に関して、
微分積分学の基本定理により、
よって、
F(x)は単調増加である。
(証明おわり)
高校で扱う連続関数(その領域内で関数が連続)はこの定理の条件を満足するので、この定理があれば十分と思いますが、
藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」に書いてあったまぼろしの基本定理:
被積分関数f(x)が連続関数(その領域内で関数が連続)で無くても、
その様に不連続な関数f(x)に対して、
その積分区間で連続な不定積分F(x)が見つかったなら、
その不定積分F(x)を使って以下の計算で定積分を計算して良い。
F(b)-F(a)
が使えます。
実際、以下の定理があります。
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)がある場合、
a<x<b
の範囲で、
F’(x)≡f(x)>0
ならば、
a≦x≦bの範囲で、
関数F(x)は単調増加である。
(定理の定義おわり)
この定理の証明に、「まぼろしの定理」を使えますが、先ずは、それを使わずに、伝統的に確立されている平均値の定理を使って、この定理を証明しておきます。
(証明開始)
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)が:
a<x<b
の範囲で微分可能で、
F’(x)=f(x)
の場合、
平均値の定理によって、
a≦x1<x2≦b
なるx1とx2に関して、
(F(x2)-F(x1))/(x2-x1)=f(x)
となるxが、
a≦x1<x<x2≦b
に、少なくとも1つ存在する。
その範囲で、
f(x)>0
なので、
F(x2)>F(x1)
である。
よって、F(x)は単調増加である。
(証明おわり)
このように証明できるこの定理は、まぼろしの基本定理を支える基礎の1つになっていると考えても良いと思います。
(備考2)
なお、全ての種類の関数における、積分前の関数f(x)と、微分前の関数F(x)との、変数xの一部の定義域での微分積分のあり得る関係が以下の図であらわせます。
(なお、F(x)として考えられる関数の、関数が連続な領域内の至るところ微分不可能な関数であるワイエルシュトラス関数等は、不連続点を持たないが、微分不可能です。)
(上図で、関数f2(x)は、除去可能な不連続点を除去した関数です。関数F(x)は、関数F(x)の不連続点を除いた変数xの範囲でf(x)の不定積分であるとともに、f2(x)の不定積分でもあります)
上図の、f(x3)とF(x3)の関数のセットの例:
以下で定義する関数のセットでは、f(x)にx=x3で除去不可能な不連続点があって、f(x)は不連続関数(その点で関数が不連続な関数であって、その点以外の領域では関数が連続な連続関数である)です。
しかし、この不連続点を持つ関数f(x)を、その不連続点を含む範囲で定積分することで定義した関数F(x)が、その不連続点の位置x3でも変数xで微分可能で、F(x)を微分すると再び不連続点を持つf(x)が得られます。
(F(x)の定義)
x≠0の場合:
x=0の場合: F(0)=0,
(導関数f(x))
この関数F(x)はx≠0の場合も、x=0の場合も、微分可能で、
その導関数f(x)は、以下の式であらわせます。
x≠0の場合の微分:
になり、xが0に近づくとー1と1の間を振動します。
この導関数が含むcos(1/x)の関数が以下のグラフであらわす形の関数になるからです。
X=0の場合にも、F(x)は微分可能で:
というように、0になります。
そのため、この導関数f(x)は、x=0で連続ではありませんが、F(x)を微分することで得られます。
この導関数f(x)は積分可能であり、積分するとF(x)になります。
この関数F(x)はx=0で連続な連続関数(その点で関数が連続)です。
F’(x)=f(x)はx=0で微分可能では無く不連続なので、x=0を含むxの範囲では微分積分学の基本定理が適用できませんが、「まぼろしの定理」が適用できるように思います。
この様な複雑な関係の中から、比較的に扱い易い連続関数(その領域内で関数が連続)を使って従来の微分積分学の基本定理が定められています。
また、大学以上の微分積分学では、積分の定義をどんどん拡張して、何でも積分できるようにして、ある関数f(x)を積分して不連続点を持つ関数F(x)を得ることができるようにし、その不連続点を持つ関数F(x)を微分して関数f(x)を得ることができるように、微分の定義も拡張するというような事も行なわれます。
そのように微分・積分の定義を拡張する入口に、微分積分の基本定理が置かれています。
そのため、微分積分学の基本定理の:
という式の意味することは:
この公式の前提条件以外の条件によってこの式と異なる結果が得られるわけでは無く、
この式を成り立たせるように、f(x)とF(x)を対応させる規則である微分と積分とを矛盾が生じ無い様に定義を修正して、この式を成り立たせているのです。
そういうわけなので、
a≦x≦bの範囲で、
F(x)が連続な関数とし、
そのF(x)が、
a<x<bの範囲で微分可能で、
f(x)=F’(x)
が有限な値で存在する場合は、
f(x)の積分の範囲の取り方を、
f(x)が、x=aやx=bで存在しない場合にも、
f(x)をaからbの範囲で積分可能にするように積分の定義を微妙に修正するだけで、
という式を計算可能にする「まぼろしの定理」を作りあげることができます。
そういう、積分の定義の修正を加えるだけで、「まぼろしの定理」が適用可能になります。
「やさしく学べる微分積分」(石村園子)の107ページの説明にある、106ページの形の微分積分学の基本定理への感想:「この定理は、f(x)の原始関数を定積分を使って定めてあるところがすばらしい」と書いてあるとおり、
素晴らしい表現だと思います。
という形の定積分を使ってf(x)原始関数F(x)を定めている本質的な表現をしているので、微分積分学の基本定理の前提である:
連結区間a≦x≦b
で関数f(x)が連続であれば:
という条件は、定積分を可能にしている条件に過ぎないことが顕わに見えています。
【まぼろしの基本定理の厳密な定義】
定積分の定義が修正されて、従来の積分の定義では不定積分F(x)が定義できなかった関数f(x)を、同じ形の定積分で不定積分F(x)を定義できるように積分の定義を修正すれば、微分積分学の基本定理が適用できる関数f(x)の種類を拡大して「まぼろしの基本定理」を構成できることが分かります。
(1)そして、そのように積分の定義を修正し、F(x)が連続関数(その領域内で関数が連続)であるという条件だけを定め、
f(x)が連続関数(その領域内で関数が連続)で無くても(積分範囲内にf(x)の関数値が存在しない不連続点があっても)積分を適用できるようにする。
(2)更に、 微分する点を含む領域内で連続な関数F(X)の微分により得ることができる関数f(x)を、以下の処理で定義することができます。
(2-1)すなわち、ある関数f(x)の不連続点x=x0で関数が極限値を持つ場合、その不連続点での関数f(x0)の値をその極限値に修正して不連続点を解消する。
(2-2)その他の不連続点については、その不連続点x=x0 を含む領域で関数f(x)を積分して関数F(x)を得て、関数F(x)を微分した場合の不連続点x=x0で導関数の値が元のf(x0)と異なる場合(例えばF(x)がx0で微分不可能で関数値が無い場合)には、関数f(x)の関数値f(x0)を、その導関数の値に修正する。
(2-3)以上の処理で定義した関数f(x)を、「まぼろしの基本定理」を適用する対象の関数f(x)とします。すなわち、定理の対象にする関数f(x)を、連続関数F(x)を微分することで得られる関数に限定します。
また、定理の対象にする連続関数F(x)も、それを微分した関数を積分することで再び得られる関数に限定します。詳しくは、連続関数F(x)を、それが微分不可能な点が散在するにしても、大部分のxの値で微分可能な連続関数F(x)に限定します。
そのように限定した関数f(x)に対して、その修正した定義による積分の計算をすると:
が成り立ち、また、次のことが成り立つ。
(3)S(x)はf(x)の不定積分である。
S(x)は連続関数(変数xの連結区間内で関数が1つながりに連続)になる。
(4)連続関数F(x)をf(x)の任意の不定積分とすると、
が成立する。
(まぼろしの基本定理の定義おわり)
このまぼろしの基本定理が 成り立つ条件を整えるために、f(x)を積分した結果の(xの連結区間内で)連続な関数F(x)を微分した導関数の関数値がf(x)の関数値と同じになるという特徴がある関数f(x)を選びました。(そうならない関数もありますが、そういう関数f(x)は除外してあります)
この「まぼろしの基本定理」を使えば:
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)がある場合:
a<x<b
の範囲で、
F’(x)≡f(x)>0
ならば、
a≦x≦bの範囲で、
関数F(x)は単調増加である。
(定理の定義おわり)
という定理を、微分積分学の基本定理を使った証明の場合と同様な手順に従って、まぼろしの基本定理を使って証明することができます。
ただし、この様に定義した関数f(x)に対して、このように修正した積分方法で積分することで得られる連続関数F(x)に限定された証明にはなります。例えば、関数が連続な領域のあらゆるところで微分不可能な関数であるワイエルシュトラス関数等は連続関数F(x)の候補として使えませんが、、、(例え候補になれても、微分が不可能なので、その関数はこの定理のF(x)の条件から外れる)。
こうして、この定理が対象にする連続関数(所定領域内で連続な関数)F(x)が、その様に定義された関数f(x)から積分することで得られる連続関数F(x)に限定されます。そして、関数が連続な領域の至るところ微分不可能な関数等が定理の対象とする連続関数F(x)から除外されます。そういうふうに、まぼろしの基本定理が対象にできる連続関数F(x)が制限されている、定理の限界によって、この証明方法で証明されるのは、そういう連続関数F(x)に係る場合だけに限定されるので、この証明方法は、全ての連続関数F(x)について定理を証明したわけでは無く、この証明は不完全です。
しかし、これにより、この定理の確からしさを確認でき、この証明方法によって定理の持つ意味が分かると考えますので、この証明方法の価値があると考えます。
また、F’(x)がa<x<bで微分可能であるという条件があるので、その条件が加わった連続関数F(x)は、まぼろしの基本定理の対象にする連続関数の集合に含まれることを証明できそうだと考えます。それが証明できれば、以上の証明方法は、「完全な証明」になり得ると考えます。
なお、この定理の対偶も正しく成り立ちますが、その対偶の一部の、正しく成り立つ定理を、以下の様に表現することができます。
【定理の対偶(の一部)】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)であり、
a<x<b
の範囲で微分可能な関数F(x)が、
a≦x≦bの範囲で、単調増加で無い
(例えばある領域でF(x)が同じ値に停留したり、減少したりする)
ならば、
a<x<b
の範囲内に、
F’(x)≡f(x)≦0
となる点が必ず存在する。
(定理の定義おわり)
(注意)先の定理(命題)の対偶は、以下の様に、定理の前提条件(関数F(x)が所定領域内で連続であること等)を否定した場合も想定した命題になります。
【定理の対偶】
a≦x≦bの範囲で、
関数F(x)が単調増加で無い
(例えばある領域でF(x)が同じ値に停留したり、減少したりする)
ならば、
(場合1)
a≦x≦b
の範囲で、関数F(x)が連続で無いか、
(場合2)
関数F(x)はその範囲で連続ではあるが、
a<x<b
の範囲で微分不可能な点があるか、
(場合3)
関数F(x)はその範囲で連続で、
かつ、 a<x<b の範囲で微分可能
ではあるが、
a<x<b の範囲内に、
F’(x)≡f(x)≦0
となる点が必ず存在する。
かの何れかである。
(定理の定義おわり)
先の【対偶の一部】は、この【対偶】における場合3を述べた命題でした。
ここで、条件付きで定義した命題は、
その条件が成立しないときには、その命題の結論が成立しない事もあるという意味を含んだ命題になりますので、
結局、上の場合1と場合2の想定は、条件付きで定義した命題の意味の中に含まれていることになります。
そのため、先の、【定理の対偶(の一部)】の命題は、
結局、定理の対偶によって表現される内容の全部を含んでいます。そのため、定理の対偶の一部では無く、定理の対偶の全体をあらわすものでした。
定理の成立条件の位置付けをこの様に解釈すると、この「定理の対偶」の定理(命題)の対偶が、以下の様にあらわせます。
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続で、
a<x<b
の範囲で微分可能な関数F(x)が、
その範囲での微分係数が全て、
F’(x)≡f(x)>0
ならば、
その関数F(x)は、a≦x≦bの範囲で、単調増加である。
(定理の定義おわり)
この命題は、元の定理ですので、元の定理が「対偶の対偶」によって再現できました。
なお、
「まぼろしの定理」 を使えば、単調増加関数F(x)の範囲を拡張した以下の定理もやさしく証明できます。
【定理】
a≦x≦b
の範囲で連続な関数F(x)がある場合:
a<x<b
の範囲で、
F’(x)≡f(x)≧0
であり、
そのうち、
f(x)=0となる点は有限個数存在するだけならば、
a≦x≦bの範囲で、
関数F(x)は単調増加である。
(定理の定義おわり)
という定理も簡単に証明できます。
積分範囲内に、F’(x0)=0となる点
x=x0が、
a≦x≦b内の、
c<d
となるcからdまでの領域内の全ての点でF’(x)=0であれば、
そのcからdまでの積分結果=0
となります。
しかし、有限の幅を持った領域にわたっては
F’(x)=0
とはならず、
所定領域内に、
F’(x)=0となる点が有限の個数有るだけならば、
その領域での積分結果>0
になるからです。
もう1つ、以下の関数F(x)が単調増加であることも、
「まぼろしの定理」を使ってやさしく証明できます。
(関数F(x)の定義)
x=0のとき: F(x)=0,
0<x≦1において、
F’(x)=1+cos(1/x),
この関数F(x)は、
0≦x≦1
の範囲内に、 無限個のF’(x)=0となる点がありますが、
0≦x≦1
の範囲内で連続、かつ、単調増加です。
このことは、
「まぼろしの定理」を使ってF’(x)を積分してF(x)を求める計算式を書けば分かります。
リンク:
高校数学の目次