
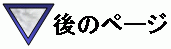
「微分・積分」の勉強
(4)極限:
高校2年生から、極限・微分・積分の「意味がわからない」「つまらない」「教わる計算方法が正しいと言える理由(証明)がわからない」で数学の学習から脱落する高校2年生が多いらしい。
その脱落の原因は、高校2年の極限・微分・積分の授業では、数学のうたい文句から外れた教育がされるからではないかと考えます。
すなわち、今までは、
「数学は、公式を正しく証明した後にその公式を使う」
と言って来たが、
高校2年生の、極限・微分・積分の授業からは、
「数学は、計算結果さえ合えば良い、途中の経緯は問わない、公式の証明は間違っていても問題視しない」
という教育思想が入り込み、
その思想の行き過ぎを避けるため、
「便利すぎる公式は、それをつかって直ぐ答えが得られてしまうから教えない」
という思想が混ざり、
数学教育に大きな濁りが入り込むので「微分積分がつまらない」となる原因があるのではないかと考えます。
その濁りに押し流され無いため、高校2年生も 公式を厳密に証明して納得してから使う、数学の心に従って極限・微分・積分の学習をして欲しいと考えます。
先ず、
「数学は公式を覚えれば良く、公式は正しく証明しないでも良い」
という誤った思想に対する数学からの警告の1つの、合成関数の極限が直感を裏切る例を以下で見ます。
【事例1】
以下の2つの図の関数:
y=f(t)
t=g(x)
の合成関数を使って、
極限を求める直感の信頼性を調べてみます。
y=f(t):

(図1)
この図1の関数f(t)はt=0で不連続です。
そのため、
t≠0の場合の
t→0 による、
f(t)→0と、
t=0の場合の
f(0)=1とが異なります。
自然数nに関して、無限数列、{tn}
tn=1/n ,
を考えることができる。
n→∞による、
tn→0 ,
である。
しかし、
n→∞による、
f(tn)→0 ,
と、
n→∞による、
f(0)→1 ,
とが異なる。
t=g(x):
(図2)
この合成関数の形を下図に描きます。
y=f(g(x))=h(x):
(図3)
直感によると、以下の各関数の式1と式2から、式3=0が成り立つように見えますが、実際は、式3=1になります。

直感によると、式1と式2から、式3=0が導かれるように思えますが、
実際は、
(1)関数f(t)が不連続であって、
関数f(t)の値の極限の値と、
変数tの極限の値t0における関数f(t0)の値と、
が異なるということと、
(2)関数g(x)がxの有限な一定範囲で極限の値t0そのものになることと、
が重なって、
直感を裏切った式3が成り立っています。
【事例2】
また、以下の合成関数では、これよりは軽症ですが、以下の様に、直感を裏切ります。
合成関数は、以下のグラフになります
【事例3】
また、以下の合成関数も、以下の様に、直感を裏切ります。
合成関数は、以下のグラフになります
(「微分積分学入門」著者:横田 壽)33ページ近くに、極限の定義が書いてあります。
関数f(x) において, x をx0 に限りなく近づけていくとき,
f(x) がある値C に限りなく近づくならば, 値C をx がx0 に近づくときのf(x) の極限値(limit) という。
x がx0 に限りなく近づくとは,
絶対値|x−x0| を限りなく小さくできるということと同じだと考えてもよいでしょう.
同様に, f(x) が値C に限りなく近づくということも
|f(x) − C | を限りなく小さくできることだと考えてもよいでしょう.
そこで,限りなく小さくできるということで考えてみると,
どんな小さな正の数 εを比較の相手と選んでも,|f(x) − C| をそれよりも小さくできるならば,つまり、変数xの値がx0に近い全てのxの値のどれであっても漏らさず、|f(x) − C| をεよりも小さくできるならば,関数値f(x)の値のバラツキを漏らさず限りなく|f(x) − C| を小さくできるといえるのではないでしょうか.
この考え方が数学でいうところの限りなく小さいということなのです.これを用いて関数の極限を厳密に定義します.
(4)極限:
高校2年生から、極限・微分・積分の「意味がわからない」「つまらない」「教わる計算方法が正しいと言える理由(証明)がわからない」で数学の学習から脱落する高校2年生が多いらしい。
その脱落の原因は、高校2年の極限・微分・積分の授業では、数学のうたい文句から外れた教育がされるからではないかと考えます。
すなわち、今までは、
「数学は、公式を正しく証明した後にその公式を使う」
と言って来たが、
高校2年生の、極限・微分・積分の授業からは、
「数学は、計算結果さえ合えば良い、途中の経緯は問わない、公式の証明は間違っていても問題視しない」
という教育思想が入り込み、
その思想の行き過ぎを避けるため、
「便利すぎる公式は、それをつかって直ぐ答えが得られてしまうから教えない」
という思想が混ざり、
数学教育に大きな濁りが入り込むので「微分積分がつまらない」となる原因があるのではないかと考えます。
その濁りに押し流され無いため、高校2年生も 公式を厳密に証明して納得してから使う、数学の心に従って極限・微分・積分の学習をして欲しいと考えます。
先ず、
「数学は公式を覚えれば良く、公式は正しく証明しないでも良い」
という誤った思想に対する数学からの警告の1つの、合成関数の極限が直感を裏切る例を以下で見ます。
【事例1】
以下の2つの図の関数:
y=f(t)
t=g(x)
の合成関数を使って、
極限を求める直感の信頼性を調べてみます。
y=f(t):

(図1)
この図1の関数f(t)はt=0で不連続です。
そのため、
t≠0の場合の
t→0 による、
f(t)→0と、
t=0の場合の
f(0)=1とが異なります。
自然数nに関して、無限数列、{tn}
tn=1/n ,
を考えることができる。
n→∞による、
tn→0 ,
である。
しかし、
n→∞による、
f(tn)→0 ,
と、
n→∞による、
f(0)→1 ,
とが異なる。
t=g(x):
(図2)
この合成関数の形を下図に描きます。
y=f(g(x))=h(x):
(図3)
直感によると、以下の各関数の式1と式2から、式3=0が成り立つように見えますが、実際は、式3=1になります。

直感によると、式1と式2から、式3=0が導かれるように思えますが、
実際は、
(1)関数f(t)が不連続であって、
関数f(t)の値の極限の値と、
変数tの極限の値t0における関数f(t0)の値と、
が異なるということと、
(2)関数g(x)がxの有限な一定範囲で極限の値t0そのものになることと、
が重なって、
直感を裏切った式3が成り立っています。
【事例2】
また、以下の合成関数では、これよりは軽症ですが、以下の様に、直感を裏切ります。
合成関数は、以下のグラフになります
【事例3】
また、以下の合成関数も、以下の様に、直感を裏切ります。
合成関数は、以下のグラフになります
(「微分積分学入門」著者:横田 壽)33ページ近くに、極限の定義が書いてあります。
関数f(x) において, x をx0 に限りなく近づけていくとき,
f(x) がある値C に限りなく近づくならば, 値C をx がx0 に近づくときのf(x) の極限値(limit) という。
x がx0 に限りなく近づくとは,
絶対値|x−x0| を限りなく小さくできるということと同じだと考えてもよいでしょう.
同様に, f(x) が値C に限りなく近づくということも
|f(x) − C | を限りなく小さくできることだと考えてもよいでしょう.
そこで,限りなく小さくできるということで考えてみると,
どんな小さな正の数 εを比較の相手と選んでも,|f(x) − C| をそれよりも小さくできるならば,つまり、変数xの値がx0に近い全てのxの値のどれであっても漏らさず、|f(x) − C| をεよりも小さくできるならば,関数値f(x)の値のバラツキを漏らさず限りなく|f(x) − C| を小さくできるといえるのではないでしょうか.
この考え方が数学でいうところの限りなく小さいということなのです.これを用いて関数の極限を厳密に定義します.
【ε-δ論法による極限値(極限の定義(その1))】
ある値C(その値Cは、εの値によらない固定値)に関して、
任意の正の数ε に対して,
0 < |x − x0| < δ のとき,
(すなわち、x ≠ x0 であるxで、上式の条件を満たす全ての実数xについて)
|f(x) − C | < ε が成り立つように
正の数δ が選べるならば,
(すなわち、その範囲の全ての実数xに対して、必ずf(x)が定義されていて、かつ、そのf(x)に関して上の式が成り立っているならば、)
である。
-----(定義の言い換え)----
大学1年生が、初めてこの定義学んだとき、定義の意味が分からず、微分積分学が分からなくなり脱落する大学1年生が多いらしい。
この定義を理解するには、想像力を膨らませて、この定義を、以下の様に噛み砕いて自分の言葉で言い換えると、この定義の意味が理解でき、定義がすんなり覚えられるようになると思います。
(0)
極限値Cを確かめるには、単に、xをx0に近づけて値Cに近い関数値f(x)を求めて行くだけで良いのではないか。
極限が有るか無いかの問題は、その方法で極限値Cを求める事ができる関数であるか、そうで無いかを判定できるだけで良いと考えます。
(A)先ず、その様にして求める事ができる極限値Cが存在する事が第1に必要な条件です。
(B)次に、その極限値Cが存在するとして、関数f(x)は、その極限値Cにどの様に近づいていかねばならないかを知る事が第2に必要な条件と考えます。
(1)
x0に近いがx0では無い実数xを考える。
(注意)
極限の定義において、xをx0に限りなく近づけてf(x)を考える際に、f(x0)を除外して考えることが極限の概念の本質的な特徴になっています。もし、f(x0)を除外しないで”極限”の有無を調べることにすると、それは、関数の”連続性”の有無を調べることになります。極限の概念は、関数が連続で無い場合も視野に入れた関数の特徴の把握のために、x0を除外して考えるという特徴を本質的に持っています。
(2)
x0から、実数値δの範囲内でずれる、x0では無い全ての実数xについてf(x)を考える。
この定義における「全ての実数x」の意味は、他の制限、例えば関数の変数の定義域を有理数だけに定めて定義域外の無理数の変数に対する関数値を考え無い事にしていても、その制限に制約されずに定義される全ての実数xを意味します。
(関数f(x)の変数xの定義域に制約されない全ての実数xを考えるということです)
(3)
その全てのf(x)の値(その値は複素数であっても良い)のバラツキの誤差を求める。
その誤差<εとするεでバラツキの範囲を定める。
(4)
(4-A)xの値のx0からずれる範囲の値δを十分小さくすれば、
その範囲内の全ての実数値のx(ただし、値x0は除外)によるf(x)の値のバラツキが小さくなり、
そのバラツキの範囲の値 ε は、
いくらでも小さな値εが得られる、
という条件が満足されるならば;
(4-B)また、そのどの実数値x(ただし、x≠x0)についても、
-ε< |f(x)-C|<ε
となる値C (この値は複素数であっても良い)が、どのように小さなεの値についても、
変わらない確固とした値で存在するならば;
その関数の値の極限が存在し、
その確固とした値C が極限値である。
----(定義の言い換えおわり)-----------
この定義の第1のポイントは:
「任意の正の数ε に対して,
0 < |x − x0| < δ という条件を満足する全ての実数x(又は複素数x)についてf(x)を考え,
その全てのf(x)に関して、その正の数εに関して、
|f(x) − C| < ε が成り立つように
正の数δ が選べるならば,
~~」
という様に、
「条件を満足する全ての実数xに関するf(x)の全てが次の条件を満足するならば、」
という説明が隠れて入っている点です。
この定義の意味は、関数f(x)がx0の近くの全ての実数xに対して関数値が定義されている関数でなければならないという事を意味します。
関数f(x)が有理数のxに関して定義されていても、無理数のxに関して定義されていなければ、関数f(x)には極限が有りません(極限が定義できない)。
この定義の第2のポイントは、
x→0を、
0 < |x − 0| < δ
(すなわち、x ≠ 0 の場合に)
として、
例えば、
f(x)→0を、
|f(x) − 0 | < ε
(すなわち、f(x) = 0 の場合を含む)
というふうに極限を定義していることです。
x→0でx≠0の場合に、
f(x)→0 (f(x)=0も含む)となる場合を
「f(x)の極限が存在する」
という極限の意味を明確にしていることです。
すなわち、
x→0 (x≠0)と、
f→0 (f=0も含む)は、
異なっていることを明確にしています。
この厳密な極限の定義によっても、
関数f(t)は、t=0での極限の値が0になり、式2が成り立っています。
この問題の本質は、
(1)
x→0の場合に、
t→t0=g(x)=0 (式1)
ではあるが、
tが、x≠0の場合でも、
t=g(x)=0
となっていること。
(t=g(x)=0は、 | t − 0 | < ε が成り立つので、式1と矛盾しない)
(2)
t→0の場合に
f(t)→0 (式2)
であるが、
t=0の場合に、
f(0)=1 ≠ 0
であること(f(t)が連続では無い)。
(3)
そのため、式3では、
x→0の場合に、
t=0であり、
f(0)=1 (式3)
となったことです。
問題の本質は、極限の定義において:
x→x0 (x≠x0)と、
t→t0 (t=t0も含む)が、
異なっていることにあります。
x→x0 (x≠x0)のときに、
t→t0 (t=t0も含む)となる、
関係に、
t→t0 (t≠t0)のときに、
f→f0 (f=f0も含む)となる、
関係を利用できる場合は:
x→x0 (x≠x0)の場合に、
t→t0ではあっても、
t≠t0である場合に限られます。
t=t0が成り立ってしまうと:
x→x0 (x≠x0)のときに、
t=t0となれば、
次は、
t→t0 (t≠t0)の場合に、
f→f0 (f=f0も含む)となる
関係は、(t≠t0という前提条件が成り立っていないので)無関係になります。
直感が錯覚したのは、この「無関係」な関係が、あたかも関係あるかのように見ることで錯覚が生まれたのです。
式1と式2が成り立っている場合に、直感の通りに、式3=0となるようにするには、極限の定義の後半の、
t→0 (t=0も含む)に整合させて、
t→0 (t≠0)におけるf(t)の極限は
t=0における関数値のf(0)に等しい値をもつこと:
「関数f(t)が連続である場合」
という前提条件を付け加える必要があります。
その場合は、直感通りに、式3=0となります。
しかし、関数g(x)が不連続なら合成関数y = h(x)=f(g(x))も不連続になるので気持ちは晴れません。
そのため、合成関数 y = h(x)=f(g(x)) を連続関数にするために、更に、
「関数g(x)が連続である」という条件も加えて、以下の定理を成り立たせます。
「微分積分学入門」(横田 壽) の42ページ近くに:
定理1.7 t = g(x) がx = x0 で連続で,y = f(t) がt = g(x0) で連続ならば,
合成関数 y = f(g(x)) も x = x0 で連続である.
(補足:日本の高校の極限と微分積分の教育)
ヨーロッパやアメリカでは、「高校で微分積分及び極限を教えるのは、直感にうったえる内容に限られ、正確な微分積分を教えられない」という理由で、微分積分は大学生に教える科目になっています。
日本の大学でも、その欧米の教育に合わせて、初めて学ぶ者に分かるように微分積分及び極限を改めて教育しているようです。
大学で使う微分積分の参考書は、高校で教える微分積分の知識を全く知らない学生に理解できるように書かれています。
しかも、大学生向けの微分積分の参考書の方が、日本の高校生向けの微分積分の参考書よりやさしく分かり易い。
高校の微分積分を勉強するなら、先ず、大学生向けの微分積分の参考書を読むことを推薦します。高校の微分・積分の教科書は分かりにくいだけで無く、間違いも含まれています。読まない方が良いのではないかと考えます。
とりあえず、大学生向けの参考書で、以前は無料でダウンロードできた「微分積分学入門」(横田 壽)を読んでみることをお勧めします。
(注:横田教授が芝浦工業大学を退官したため、この教科書を無料で掲載していたWebページが無くなりました。この本は書店で購入できます。)
(しかし、同じ著者の書いた高校生向けの参考書「確実に身につく微分積分(2012年)」の1版は、内容が劣化しているのでお勧めできません。大学生向けの本物の知識の参考書「微分積分学入門(2004年)」を読んでください。)
「微分積分学入門」(横田 壽)の読み方は、 66ページから始まる2章「微分法」の以前のページは斜め読みして、何が書いてあるらしいかを漠然と把握しておいて、2章「微分法」以降を精読することをお勧めします。読んでいるうちに知らない関数や概念が出てきたら、66ページ以前に書いてありますので、探して、その部分を読んで理解するように勉強してください。
リンク:
高校数学の目次









0 件のコメント:
コメントを投稿